自分の話ばかりしてしまうのは、決して性格が悪いからではない。
実際、ハーバード大学の研究では、人は自分について話すと脳内で快感を司る領域が活性化し、ドーパミンという“うれしい気持ち”を生む物質が出ることが分かっている。
つまり、自分の話をしたくなるのは、人間の脳の自然な反応なのである。
とはいえ、会話は相手あってのものだ。
自分の話ばかりしていては、相手は疲れ、次第に距離を置かれるようになる。
人間関係を大切にしたいのであれば、「聞く力」を育てることが不可欠である。
そのためには、いくつかの実践的な方法を身につけるとよい。

まず、自分と相手がどれくらい話していたかを意識する癖をつけることが大切だ。
理想的な会話のバランスは、自分3割・相手7割くらいである。
自分が3分以上連続して話していたら、少し立ち止まり、相手に質問を返すようにする。
会話のあとに「自分は今どれくらい話していたか」を軽く振り返るだけでも、話しすぎる傾向に気づけるようになる。
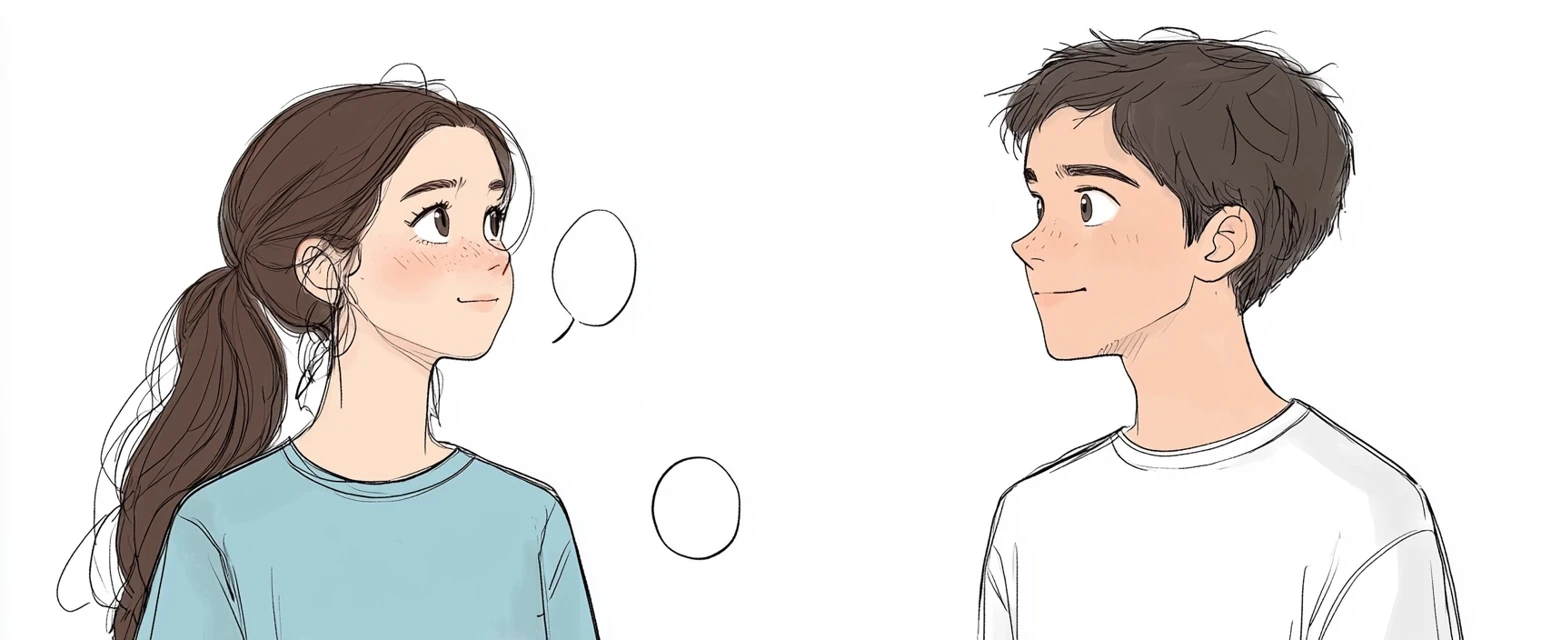
次に、質問の仕方を工夫すると、自然に相手の話を引き出すことができる。
「いつ?」「どこで?」「なぜ?」「どうやって?」といった質問の型をいくつか頭に入れておくと、話の流れに応じてスムーズに問いを投げられるようになる。
あらかじめ質問の“引き出し”を作っておくことで、会話に余裕が生まれる。
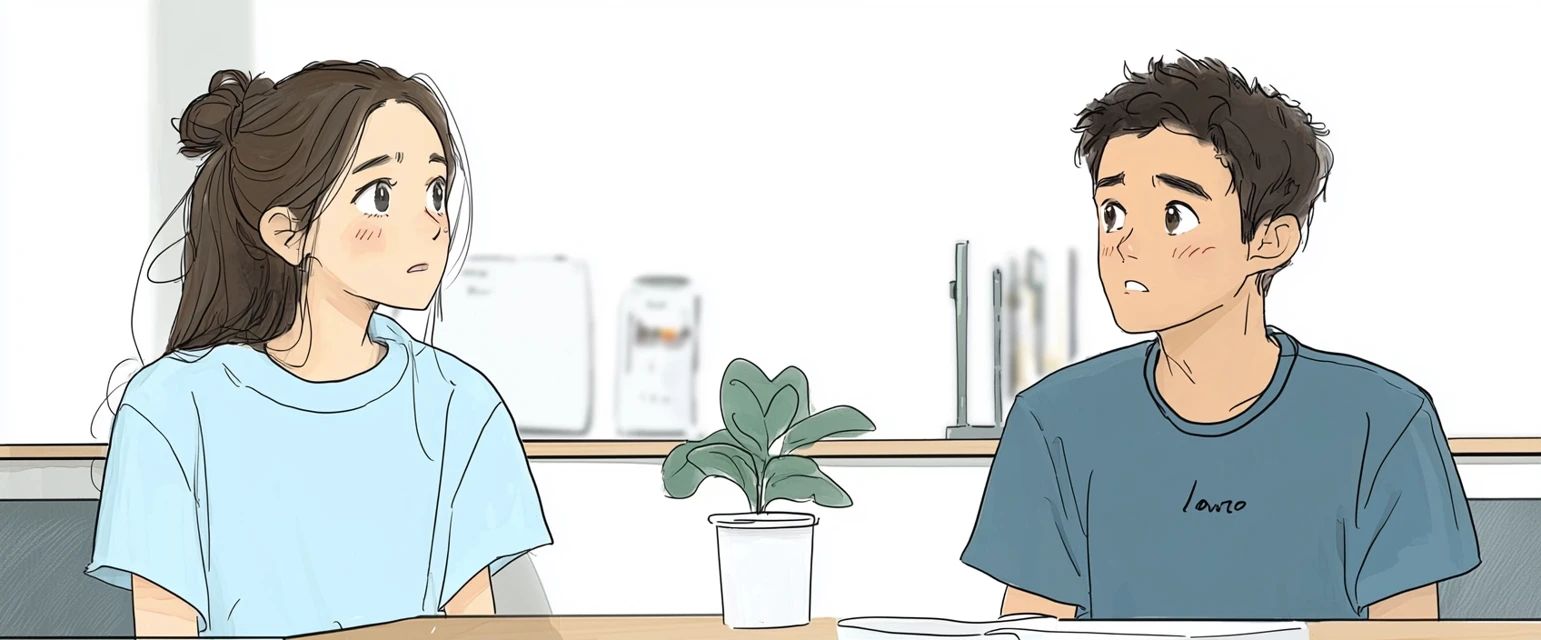
相手の話に興味が持てないと感じたときも、すぐに自分の話に切り替えないよう気をつけたい。
最初は演技でもよいので、「それでどうなったの?」「へえ、どうしてそう思ったの?」と興味を持つふりをしてみるのが効果的だ。
脳には「演じることで本気になる」性質があり、関心があるふりをしているうちに、本当に面白く感じられることも多い。
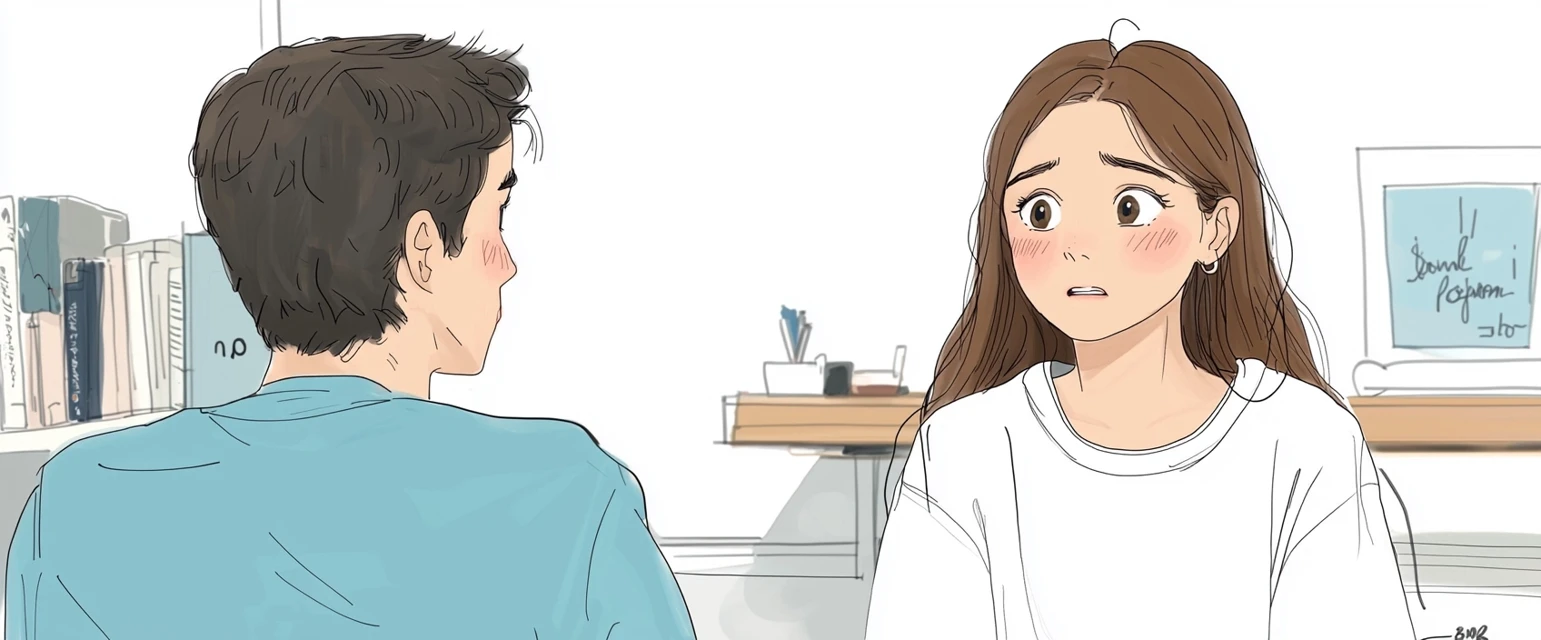
また、沈黙を恐れてすぐに自分の話で埋めようとするのも、自己中心的な話し方の特徴である。
話の流れの中で、少し間を置くことを意識してみるとよい。
相手が考える時間を持てるようになり、自然なやりとりが生まれやすくなる。
話したい気持ちが高まったときこそ、一拍置いて「あなたはどう思う?」と返す習慣をつけることが重要である。
そして、どうしても自分の話をしたくてうずうずしてしまう人には、話したいことをあらかじめノートに書き出す方法も有効である。
自分の思いや考えを紙に吐き出すことで、頭の中が整理され、話したい衝動もおさまりやすくなる。
こうした“頭の中の排出”を習慣にすれば、相手の話に心を向ける余裕ができるようになる。
自己中心的な話し方は、多くの場合、無意識のクセやちょっとした不安から生まれている。
それを責める必要はないが、放っておけば人間関係の距離が開く原因にもなる。
だからこそ、自分を客観的に見直し、小さな行動を重ねていくことが大切なのである。



コメント