休みの日になるととことん寝たくなるという人は多い。
平日は朝早く起きて仕事や学校に行き、睡眠時間が十分に確保できないため、休日こそ寝不足を解消したいという気持ちになるのは自然なことだ。
しかし実はこの「寝だめ」行動には、体内リズムとのズレが隠れている。
これを「社会的時差ボケ」と呼ぶ。
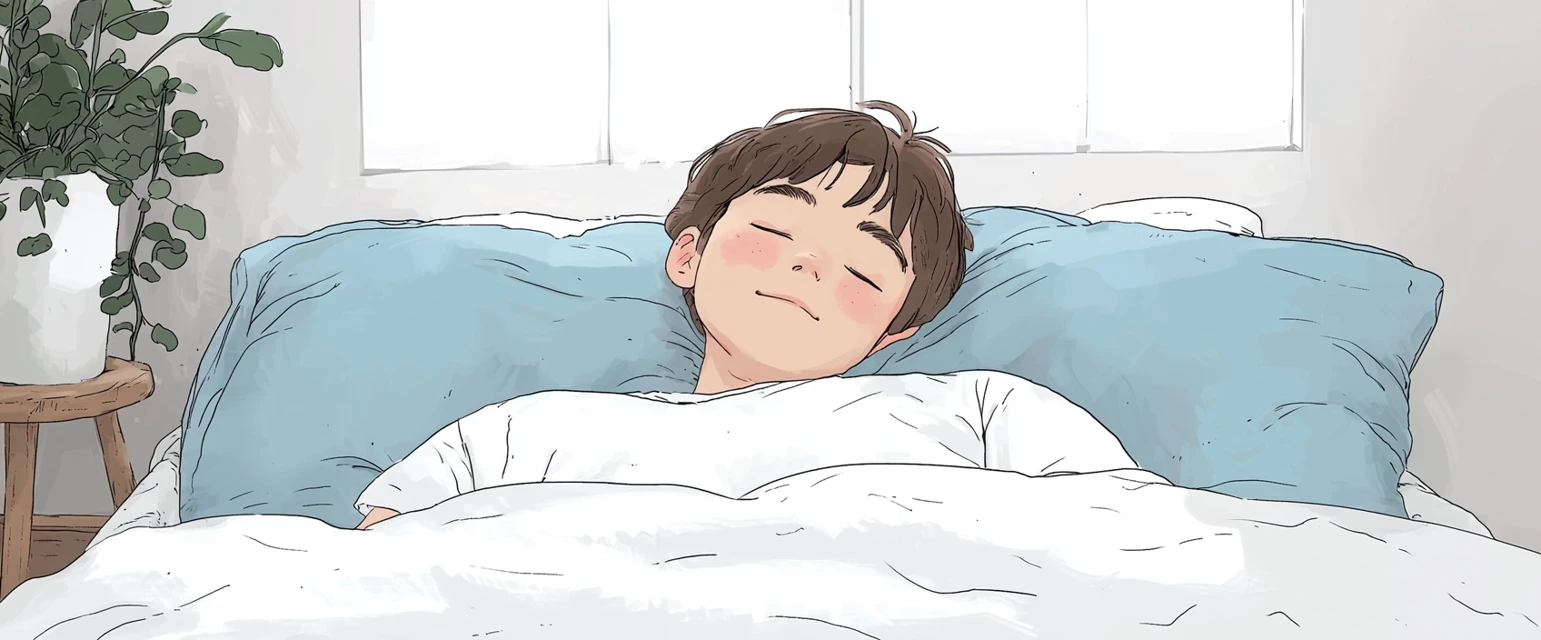
社会的時差ボケとは、平日の生活スケジュールと休日のスケジュールの間に生じる、体内時計のズレのことである。
たとえば、平日は朝7時に起きているのに、休日は11時まで寝ているとする。
すると、平日と休日の起床時間には4時間もの差がある。
これは日本とインド間の時差に近く、体にとっては週末ごとに海外旅行をしているような負担となる。
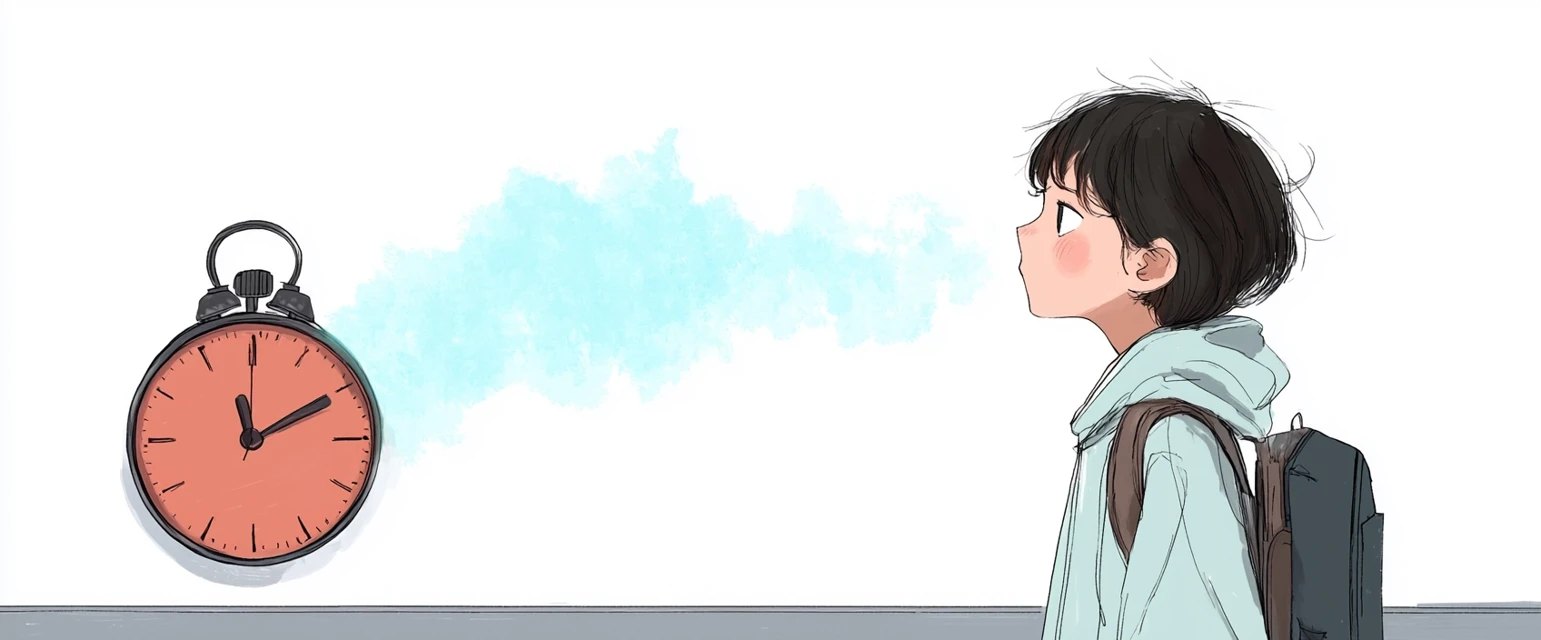
人間の体には本来、生まれつきの体内リズム、いわゆる「クロノタイプ」がある。
朝型の人もいれば、夜型の人もいる。
夜型の人が社会のスケジュールに合わせて早起きを続けていると、平日の生活は体にとって“無理をしている”状態になる。
その無理を取り戻すように、休日には本来のリズムに戻ろうとするため、長く眠ってしまうのだ。

このような生活を続けていると、週末に生活リズムが大きく崩れ、日曜の夜に寝つけず、月曜の朝がつらくなるという悪循環に陥りやすい。
また、時差ボケのような状態が続くことで、集中力の低下、気分の落ち込み、代謝の乱れなど、心身への影響も指摘されている。

できるだけ平日と休日の起床時間の差を小さく保ち、遅くまで眠る代わりに、夜に早く寝ることで睡眠を補う方が、体への負担は少ないとされている。
また、朝起きたらカーテンを開けて日光を浴びることで、体内時計がリセットされ、自然なリズムが整いやすくなる。
つまり、休みの日にとことん寝たいという欲求は、体が普段の生活に無理をしているというサインとも言える。
毎週末に長く寝ているという人は、一度自分の生活リズムを見直してみるとよいだろう。
それは、疲れを取る以上に、自分の体と心を整える第一歩になるかもしれない。



コメント