生きづらさとは、痛みや苦しみそのものではなく、「何かが違う」という違和感のような感覚である。
それは多くの場合、自分の内面と社会、あるいは自分の理想と現実との間に生じたズレに由来している。
たとえば、自分が本当に望んでいることと、周囲から期待されていることが一致しないとき、人は無意識にそのズレを感じ取って心が重くなる。
また、自分の本音を押し殺して、社会の中で「正しそうな自分」を演じているときも同様である。

このような状態が続くと、「自分は間違っているのではないか」「自分には価値がないのでは」といった否定的な思考が浮かびやすくなる。
その背景には、脳の働きや心理的な防衛機制が関係している。
人の脳には、デフォルト・モード・ネットワークと呼ばれる、ぼんやりしているときに活性化する領域がある。
この領域は、過去の出来事の反芻や未来への不安、他人との比較といった思考に関わっており、これが過活動になると生きづらさが強まる。

また、人は心の傷から身を守るために、自分でも気づかないうちに本音を抑え込んだり、無理に正当化したりすることがある。
こうした心理的な反応は短期的には心を守るが、長期的には自分らしさを見失う原因にもなる。
たとえば「まあ、仕方ない」と何度も自分を納得させるうちに、本当の気持ちが分からなくなってしまうことがある。

このような状態を乗り越えるためにまず必要なのは、自分が感じていることに対して「これは間違っていない」と認める姿勢である。
多くの人は生きづらさを感じると、「自分が弱いせいだ」「もっと頑張らなければ」と思いがちだが、そうした自己否定はかえって苦しさを深めてしまう。
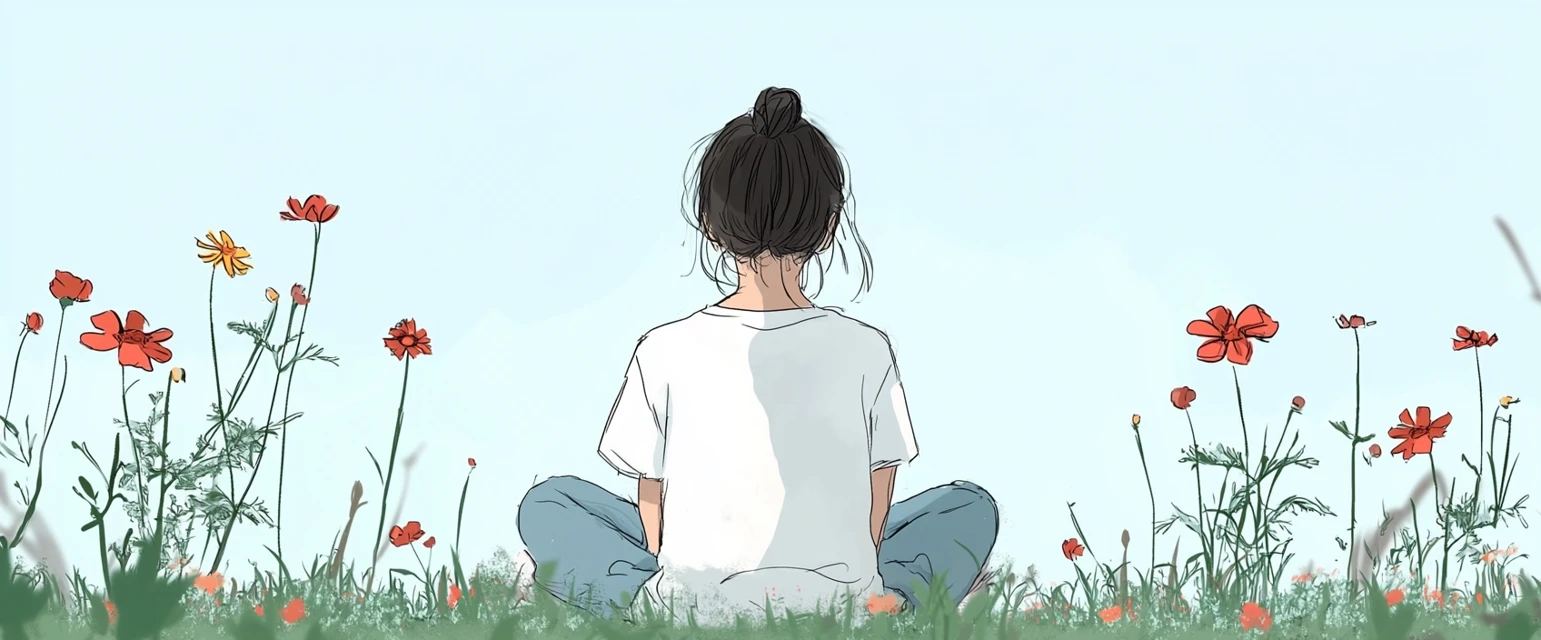
実際には、生きづらさの背景には社会的な構造の問題もある。
すべてを個人の努力や性格のせいにしてしまうと、見えにくくなってしまうものがある。
たとえば、成果主義や過度な自己責任論が強い社会では、誰もが自分の「正解らしさ」を探し続けることを求められる。
その一方で、個性や違和感を受け入れる余白はどんどん狭くなっている。
そうした社会の中で生きている限り、感じる生きづらさには個人の責任だけではなく、環境要因も含まれているという視点が必要になる。

ではどうすれば、心を少しでも軽くできるのか。
神経科学の研究によれば、強い感情は90秒ほどで生理的ピークを迎え、あとは思考がそれを引き延ばしているとされる。
つまり、つらさや怒りを感じたときも、まずは深呼吸して90秒待ってみるだけで、波が自然に静まることもある。
これだけでも、感情に飲み込まれずにすむための小さな足がかりになる。
さらに、最近の心理療法では、感情を無理に消すのではなく、その感情の奥にある価値を探るという方法が重視されている。
たとえば、不安の裏側には「本当は誰かとつながりたい」という願いがあるかもしれないし、怒りの裏には「もっと自分を大切にしたい」という感情があるかもしれない。
こうした感情の声に耳を傾けることで、自分が何を大切にしているのかが見えてくる。
そして、その価値に向かって少しずつ行動することが、息苦しさの中に小さな意味や方向性を取り戻す手がかりとなる。
生きづらさを感じやすい人は、たいてい感受性が豊かで、他人の気持ちに敏感で、自分と世界とのズレに気づける力を持っている。
その感性は、ときに苦しみを生むが、同時にまだ見ぬ可能性や変化の芽を教えてくれる。
だからこそ、生きづらさは単なる障害ではなく、自分らしく生き直すための大切なサインなのかもしれない。



コメント