「自分には特技がない」と感じる人は少なくない。
だが、実際には多くの人が、自分の中にある特技に気づいていないだけである。
例えば、人の話をよく聞けることや、時間を正確に守れること、地図を見ずに目的地に着けることなど、本人にとっては当たり前でも、他人から見れば十分に特技と呼べるような能力は多い。
このような自己評価のズレは、心理学でも説明されている。
ドニング=クルーガー効果と呼ばれる現象では、能力の低い人ほど自分を過大評価し、逆に一定のスキルを持つ人は、自分の能力を過小評価する傾向がある。
つまり、「自分には特技がない」と思っている人ほど、実は人並み以上のスキルを持っている可能性もある。
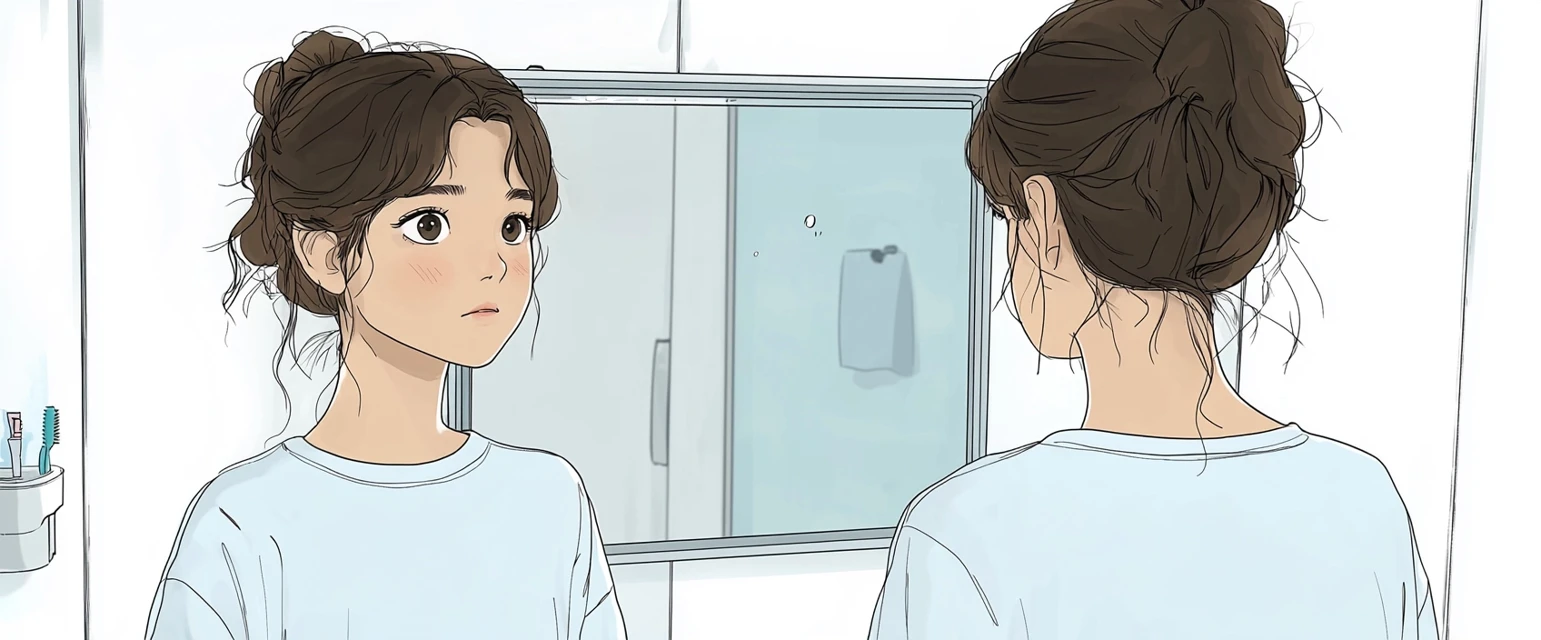
また、特技とは「社会的に見せやすい技能」と思われがちである。
たとえば、ピアノが弾ける、英語が話せる、スポーツが得意など、いわゆる“披露できる特技”ばかりが注目されやすい。
だが、本来の特技とは、その人が自然に行えること、努力せずとも他人よりうまくできることであり、必ずしも派手である必要はない。
むしろ、目立たない能力のほうが、集団の中で安定的な役割を果たすこともある。
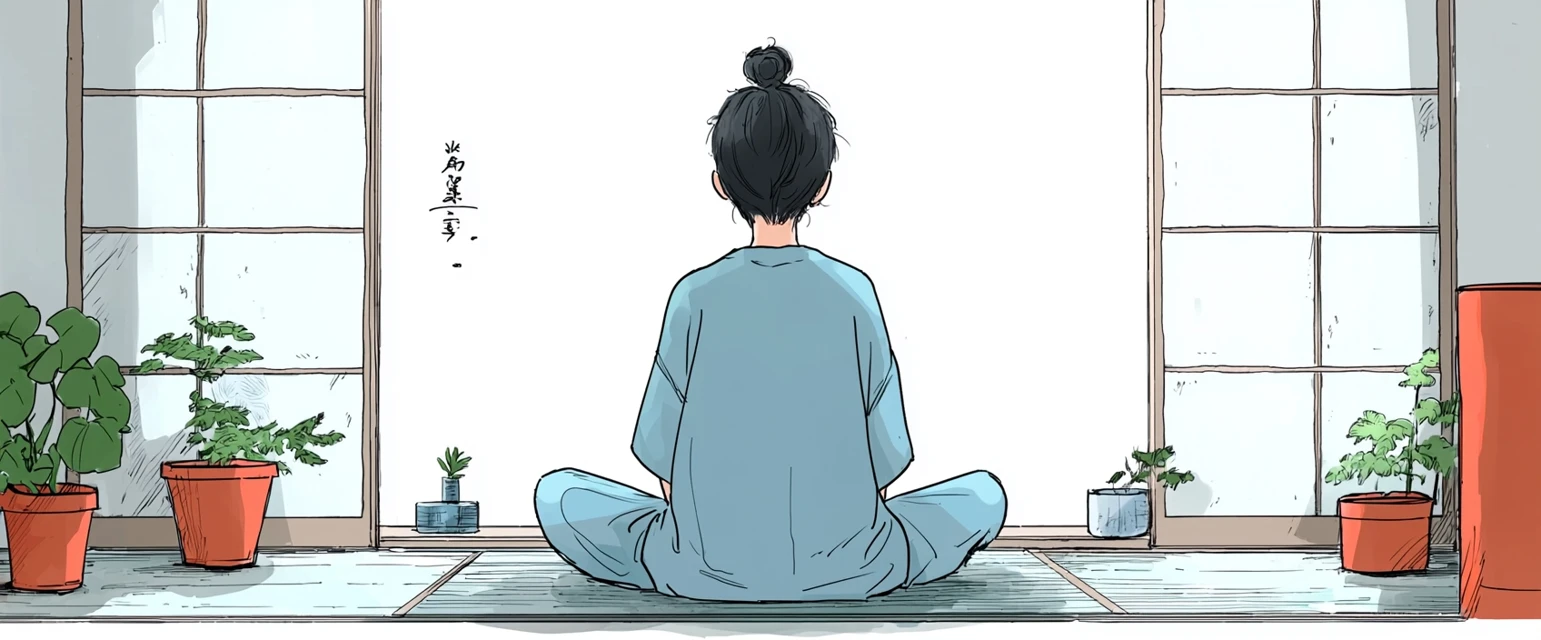
特技がないと感じやすい背景には、文化的な要因もある。
日本社会では、謙遜が美徳とされる傾向が強く、自分の得意なことを口に出すことに抵抗を感じる人が多い。
とくに幼少期から「出しゃばらないように」と教えられてきた人ほど、「得意なことを話すのは恥ずかしい」と感じやすい。
結果として、自信を持てる能力があっても、それを特技と認識できなくなってしまう。

近年では、そもそも「特技」という概念自体が変化しつつある。
これまでのように一つのことを極めるよりも、複数の分野に興味を持ち、柔軟に移動できる人が重宝される時代になってきている。
ひとつの特技に縛られていない状態は、むしろ自由で、変化に強いとも言える。
「特技がない」とは、言い換えれば「まだ何者でもない状態」であり、それは大きな可能性でもある。

脳科学の観点からも、特技とは「もともと備わっていた才能」ではなく、「やっているうちに快感を覚え、繰り返すことで磨かれたスキル」であることが多い。
つまり、何かを始めることで脳のやる気回路が刺激され、次第に得意になっていく。
逆に言えば、「特技がない」とは、まだ自分にとって心地よい刺激と出会っていないというだけのことなのだ。

一方で、現代のSNS環境は「他人との比較」を助長し、自分の能力を低く感じさせやすい。
他人が投稿するスキルや成果ばかりを目にすることで、「自分には何もない」と思い込みやすくなってしまう。
しかし、ネット上で目立つスキルだけが価値あるものではない。
人の気持ちを察する力、日常を丁寧に暮らす力、同じことを地道に続けられる力などは、可視化されにくいが、社会に欠かせない力である。
創作や芸術の分野でも、「才能があるから始める」のではなく、「とりあえず始めたことが後から特技になった」という例は多い。
表現の世界では、始めることそのものが意味を持つ。
結果的に身についた技術が「特技」と呼ばれるようになるのであって、最初からそれを持っていた人はむしろ稀である。
さらに、宗教や哲学の視点では、「特技がない」という状態自体に価値があるという考え方も存在する。
仏教では「自然体であること」が理想とされ、「何者かになろうとする執着」こそが苦しみの原因とされる。
また、キリスト教的な思想においては、人間の価値は行動や成果に基づくのではなく、存在そのものにあるとされている。
つまり、特技があるかどうかに関係なく、人はすでに価値ある存在として認められているのだ。
結局のところ、「特技がない」という状態は決して否定されるべきものではない。
それは未定義で自由であり、どのようにも展開できる可能性を含んでいる。
むしろ、「これが自分の特技だ」と決めてしまうことで、新しい可能性を閉ざしてしまうこともある。
特技は探すものではなく、気づけば身についていたもの。
焦らず、比べず、まずは好奇心のままに手を動かしてみることが、結果として最も自然な形の“特技”を育てることになる。



コメント