ウミガメは自分が生まれた浜辺に戻り、産卵する習性を持つ。
この現象は「母浜回帰(ホーミング・ビヘイビア)」と呼ばれ、科学者たちにとって長年の謎とされてきた。
ウミガメは孵化するとすぐに海へと向かい、何年もの間広大な海を回遊した後、成熟すると驚くべき精度で自分の生まれた浜へ戻ってくる。
この不思議な行動には、いくつかの生物学的な仕組みが関わっている。
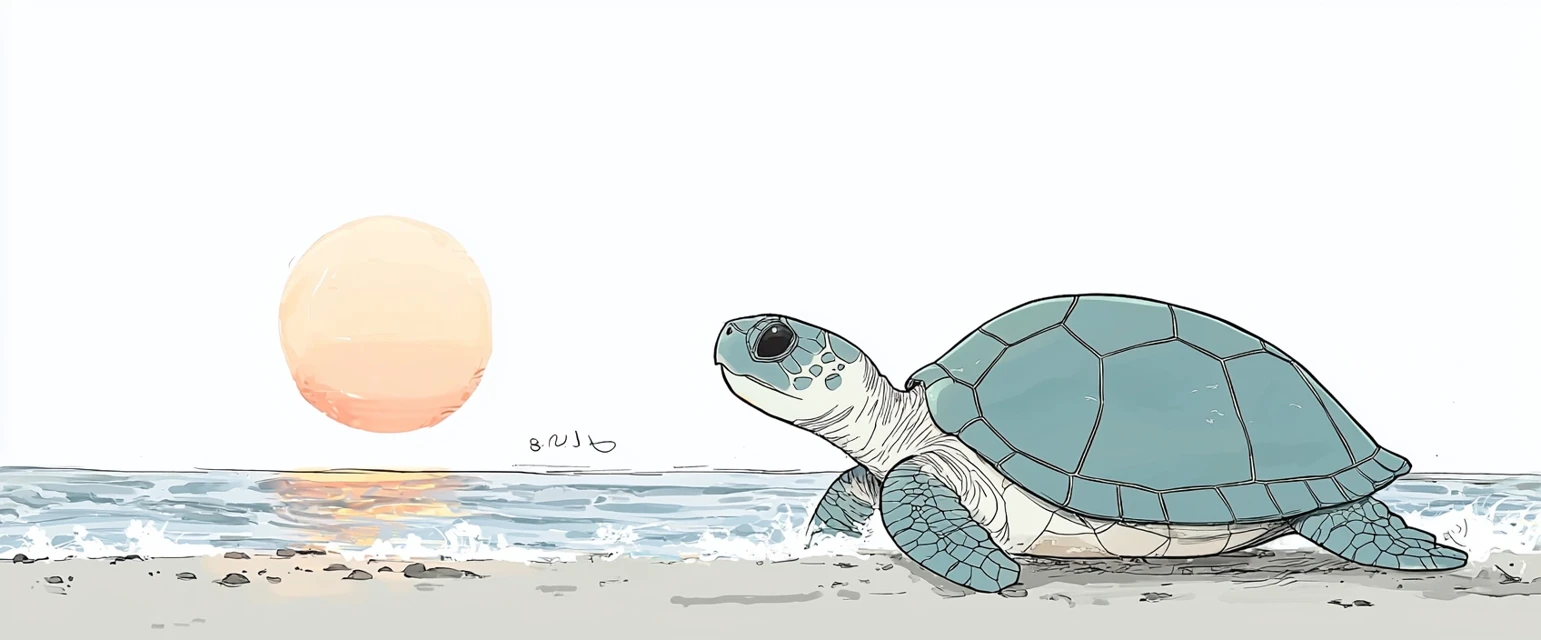
ウミガメが生まれた浜を記憶する方法の一つとして、「地磁気を利用したナビゲーション能力」が考えられている。
地球には場所ごとに異なる磁場があり、ウミガメは孵化時にこの「地磁気の指紋」を記憶するとされている。
成長して回遊を続ける間も、地磁気の微妙な変化を感知し、自分の生まれた浜と同じ磁場のパターンを探しながら移動することで、帰巣を果たすと考えられている。
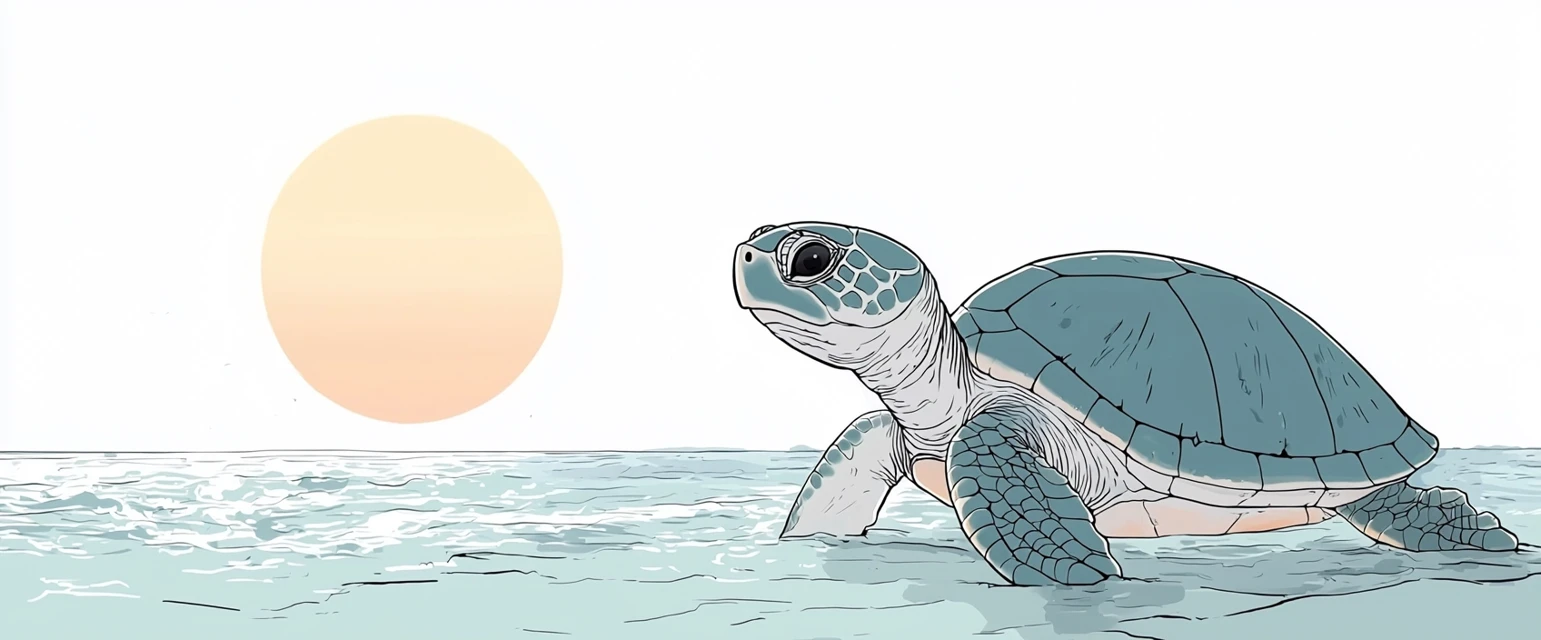
また、海水の化学的な成分や匂い、潮の流れなどの環境要因も手がかりになっている可能性がある。
ウミガメは嗅覚が発達しており、特定の浜辺の水の組成を記憶しているのではないかとする説もある。
サケが産卵のために生まれた川へ戻る際に、川の匂いを頼りに遡上するのと似た仕組みが働いているかもしれない。
ウミガメは成熟するまでに10年から50年ほどかかるとされ、個体によって回遊ルートも異なる。
しかし、産卵の時期が来ると長い旅を経て、驚異的な精度で生まれた浜へ戻る。
産卵は主に夜間に行われ、メスは砂浜を掘り、100個前後の卵を産み落として砂で覆い隠す。
孵化した子ガメは、再び海へと旅立ち、このサイクルを繰り返していく。
この習性がウミガメの生存戦略として長年機能してきたが、近年では気候変動や開発による浜辺の消失、海洋汚染などが深刻な脅威となっている。
ウミガメが戻るべき浜辺が失われたり、人工的な光が夜の浜を照らしてしまうことで、産卵や孵化後の海への移動が妨げられるケースも増えている。
そのため、各国ではウミガメの産卵地の保護活動が進められており、人工孵化や保護プログラムなども行われている。
ウミガメの帰巣本能は、単なる本能的な行動ではなく、磁場や環境情報を精密に感知し、長い年月を経て再び同じ場所へ戻るという、自然界の驚異的な仕組みの一例である。
今後の研究によってその詳細がさらに明らかになれば、動物のナビゲーション能力の解明につながるだけでなく、ウミガメの保護活動にも大きな役割を果たすだろう。



コメント