メモを取らずに物事を覚える人がいる。
一見すると記憶力が特別に優れているように見えるが、実はその背後には心理学的な仕組みが働いていることがある。
たとえば、「意図的な忘却」という現象がある。
これは脳が不要と判断した情報を積極的に忘れようとする働きのことだ。
メモを取らずに情報を覚えようとする場合、脳は「これは重要だ」と判断しやすくなり、記憶への優先度が上がる。
逆にメモを取ると、「あとで見返せばいい」と油断し、記憶の定着が弱まる。
この現象は「Google効果」や「デジタル・アメンジア」とも呼ばれており、現代人に広く見られる傾向である。
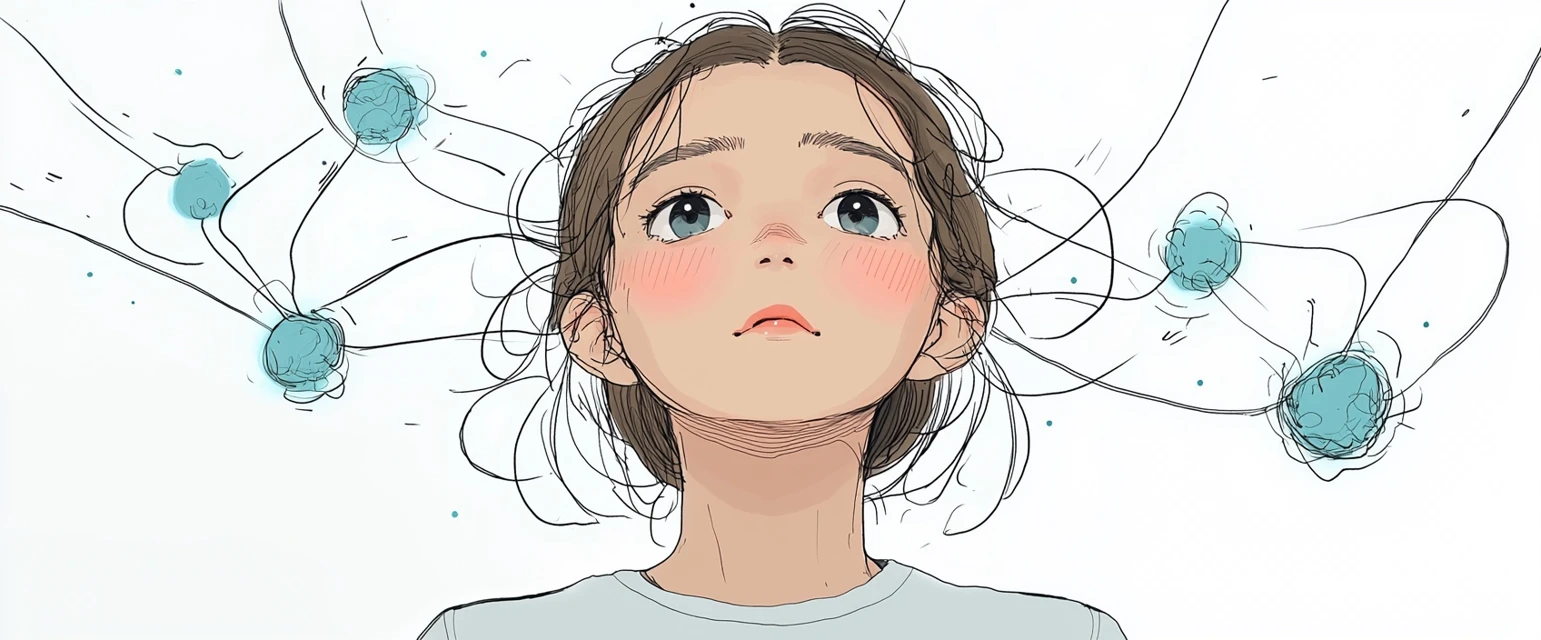
また、覚える努力そのものが記憶を助けるという考え方もある。
これは「生産的記憶努力」と呼ばれ、自分の力で思い出そうとすることで、脳の活動が高まり記憶が深まるというものだ。
何かを自力で思い出す行為は、ただ情報を目で追うよりも、はるかに強く記憶に残る。
このとき、脳は情報を意味のまとまりとして整理しようとする。
これを「チャンク化」といい、人は単語や事実をそのまま記憶するのではなく、意味を通じて圧縮し、関連づけながら覚えているのである。
さらに、メモを取らないことで生まれる「覚えなければならない」という意識も記憶に影響する。
これは「メタ記憶」と呼ばれる、自分の記憶に対する自覚的な判断に関係している。
この意識が高まると、脳内では集中力や緊張感を高める神経伝達物質が働き、記憶の定着を助けることが知られている。
つまり、プレッシャーが良い意味で記憶力を引き出すことがあるのだ。
ただし、これは必ずしもメモを取らない方が良いという意味ではない。
メモは外部記憶として機能し、情報の整理や共有には欠かせない。
大切なのは、メモに頼りきることで記憶の努力を放棄しないことである。
覚えるべき情報を意識的に選び、時には意図的に記憶に挑戦する姿勢こそが、学習や記憶をより深いものにしてくれる。



コメント