「妥協して結婚した」という言葉には、どこかネガティブな響きがある。
しかし、心理学や社会学の研究を参照すると、理想の相手を追い求めた末に結婚した人よりも、ある程度の現実的な判断で結婚に踏み切った人の方が、長期的な満足度や幸福度が高い傾向があるという、興味深いデータがある。
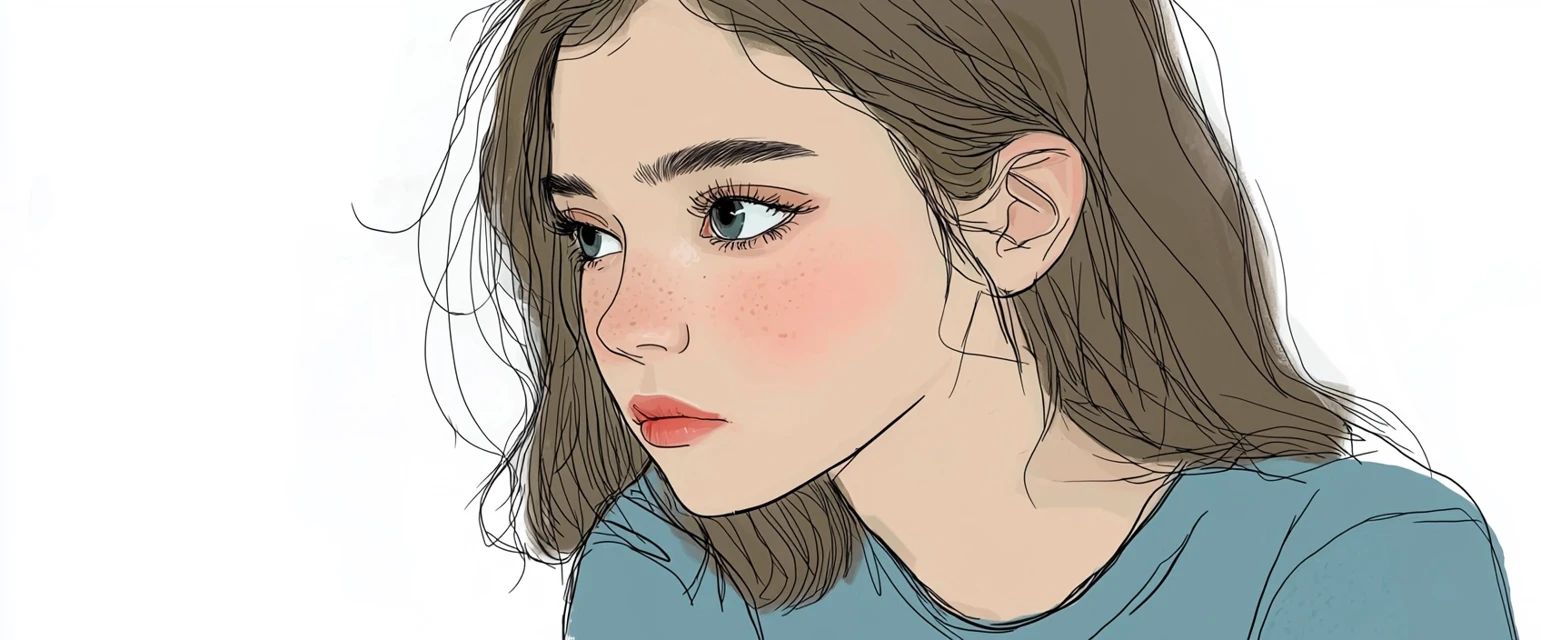
アメリカのラトガーズ大学が実施した研究では、パートナーに対して高すぎる理想を抱く人ほど、結婚生活における不満や後悔を感じやすいという結果が出ている。
理想像が具体的であればあるほど、実際の相手との差分が強調され、そのギャップが日々の不満につながるのだ。
一方で、妥協を受け入れて結婚した人々は、最初から「完璧な相手など存在しない」という前提を持っているため、現実の相手をあるがままに受け入れる姿勢を取りやすい。
このような人々は、パートナーに対して過剰な期待をせず、小さな思いやりや配慮に対しても感謝を感じやすいという特徴を持つ。

心理学における「期待−現実ギャップ」の理論によれば、期待が高すぎると現実に対する失望が生まれやすく、逆に期待が控えめであるほど、日常の些細な満足が幸福感を生む傾向がある。
妥協して結婚した人は、この期待値の調整が自然にできているため、結果として結婚生活の中でポジティブな感情を得やすいのである。
また、アメリカの社会学者ペッパー・シュワルツ博士の調査によれば、パートナーに現実的な期待を持っていた人々は、結婚満足度が高く、離婚率も低い傾向があることが示されている。
恋愛における初期の情熱は時間と共に薄れる一方で、協調性や信頼関係は年月を経るごとに強まりやすく、こうした安定した関係性こそが長期的な幸福の土台となる。
妥協という行為は、一見すると自分を偽る選択のように思われがちだが、実際には人間関係の本質を見極めた結果とも言える。
相手の欠点も含めて受け入れ、そのうえで関係を築こうとする態度は、理想を追い続けるよりもはるかに成熟した判断であり、結果的に幸福に結びつきやすいのである。
完璧な相手を求めることがロマンチックだとされがちな現代において、妥協という言葉の裏にある現実的な選択は、むしろ堅実で賢い道かもしれない。
理想を一歩手放したところから、本当の意味での幸せな結婚生活が始まる可能性は十分にある。


コメント