他者に手を差し伸べることが、なぜこんなにも私たちを幸福にするのだろうか。
これは単なる道徳的な満足だけにとどまらない。
実は、私たちの体と心は、他者貢献によって深く豊かに反応する仕組みを持っているのである。
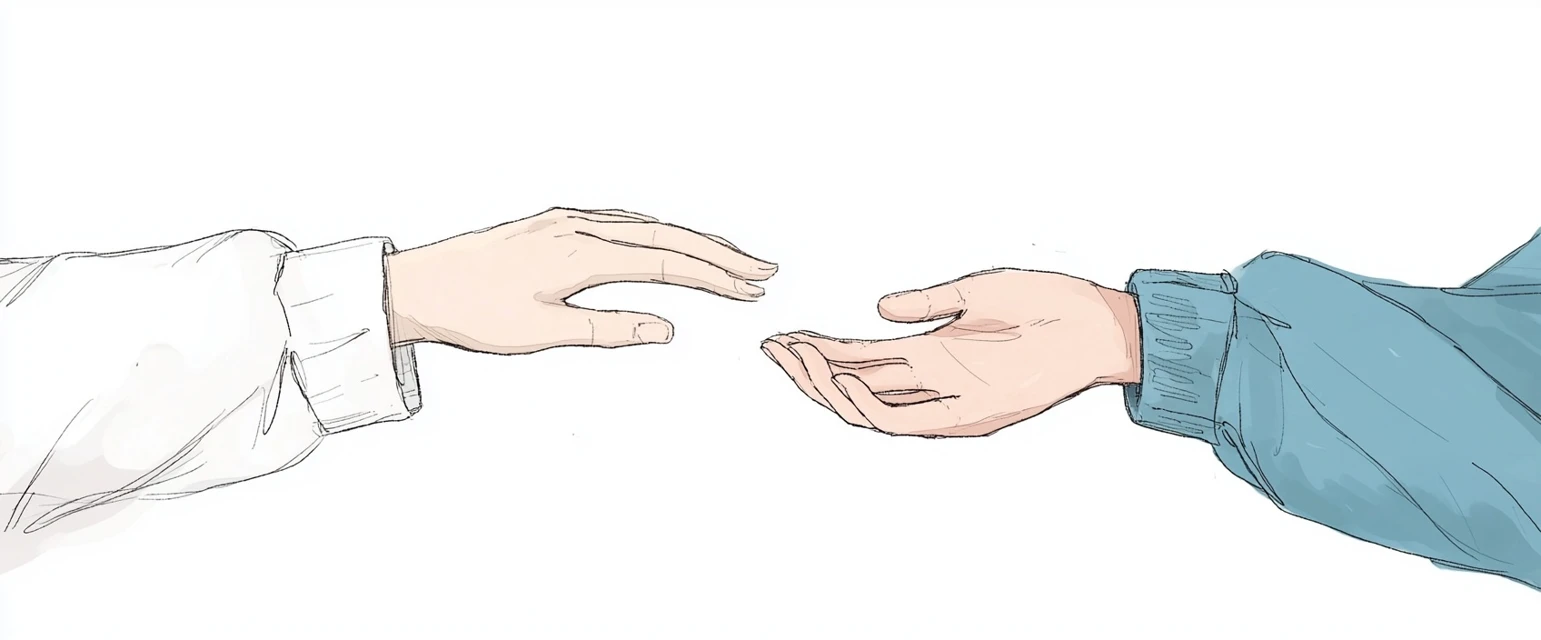
まず、生理的な観点から見てみると、他者に親切な行動を行うと、脳内でエンドルフィンやオキシトシン、さらにはドーパミンといった「幸福ホルモン」が分泌される。
これらのホルモンは、リラックス効果や自然な高揚感をもたらし、ストレスを軽減するのに役立つ。
特にドーパミンは、私たちの「報酬系」を刺激し、再びその行動を繰り返したいと思わせる。
この生理的な反応が、他者貢献の行動を持続させる大きな理由となっている。
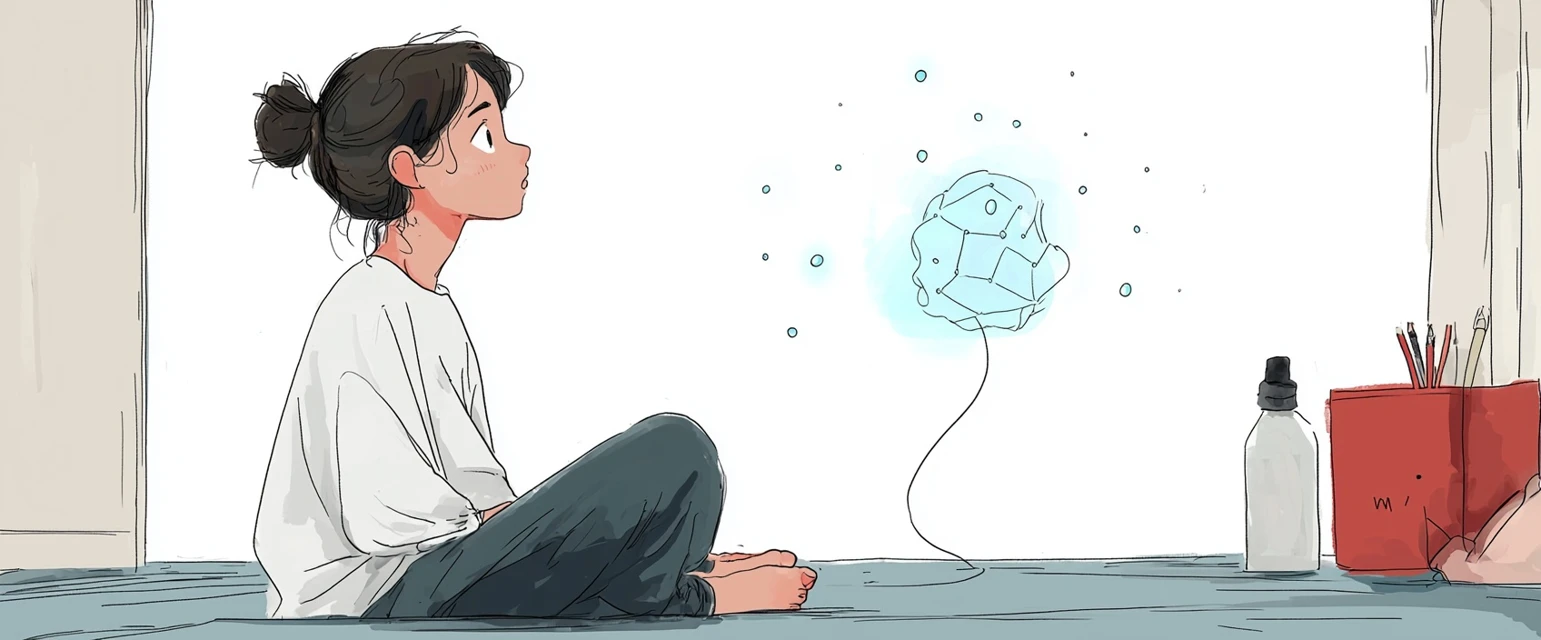
次に、心理的な側面を考えてみよう。
親切な行動は、ポジティブな感情を増やすだけでなく、ネガティブな感情を和らげる効果がある。
これにより、ストレスや不安に対する耐性が強化される。
また、他者に貢献することで自己超越の感覚を得ることができる。
自己中心的な視点から離れ、大きな意義や目的を感じられるようになる。
これが「フロー状態」と呼ばれる没頭感を生み出し、深い満足感をもたらすのだ。
社会的なつながりの面でも、他者貢献は重要な役割を果たしている。
他者に貢献することは、ソーシャルサポートを強化する。
つまり、自分が困難に直面したときに、周囲から助けを受けやすくなる。
こうした相互支援のネットワークは、心理的にも物理的にも健康を維持する基盤となる。
また、協力し合う文化を育むことで、コミュニティ全体のレジリエンス、すなわち困難を乗り越える力が高まる。
これにより、社会全体がより安定し、幸福な状態を保つことができる。
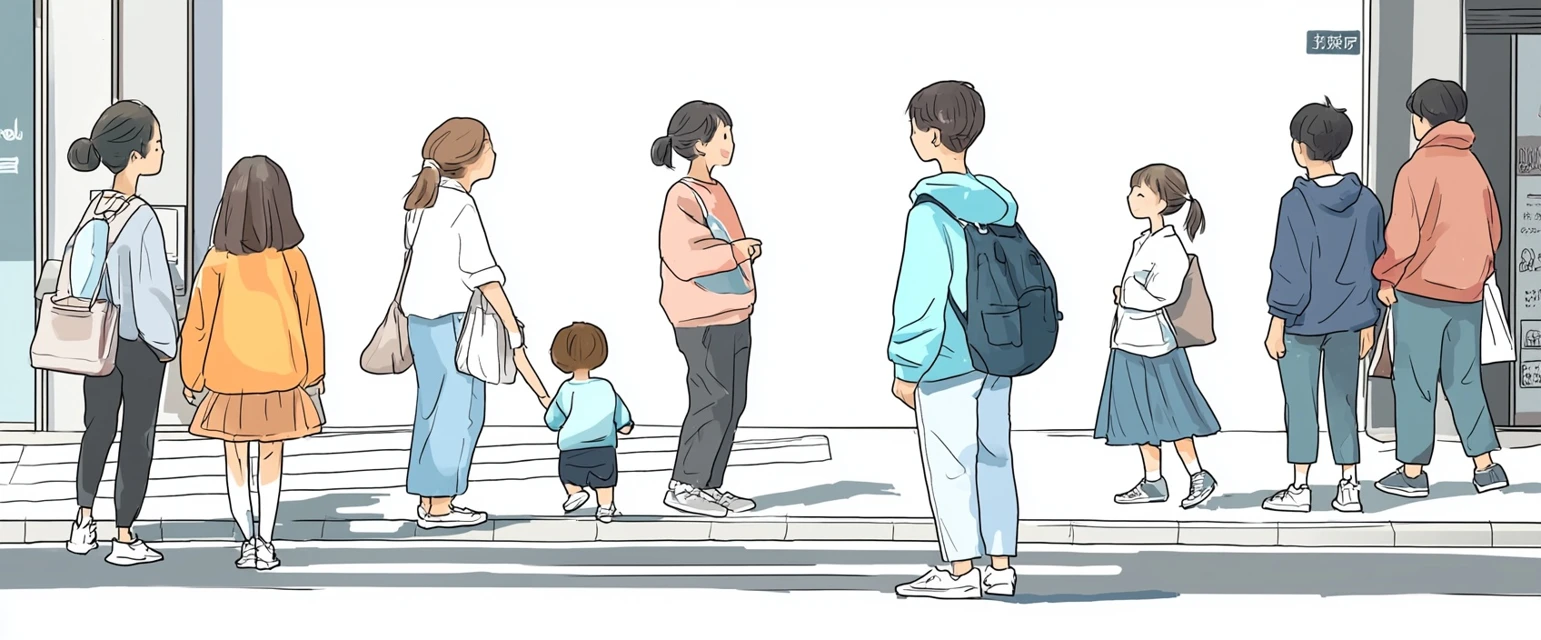
さらに、他者貢献はポジティブな行動の連鎖を引き起こす。
人は他人の行動を観察し、模倣することで学ぶ。
したがって、貢献行動を目にすることで、他の人もその行動を真似しやすくなる。
このような循環は、短期的な快楽を超え、長期的な幸福感の構築に寄与する。
自己成長や人間関係の質を向上させることが、持続的な幸福感をもたらす要因となる。
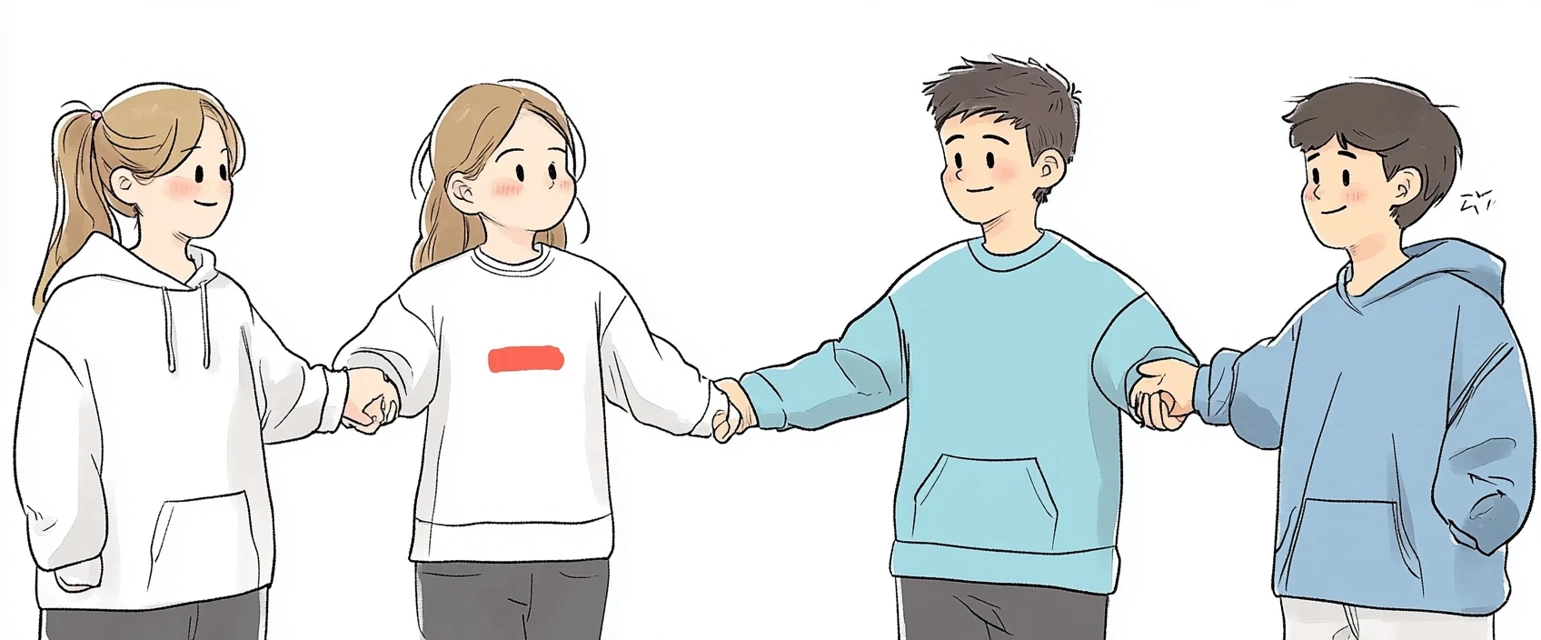
経験的なデータもこれを裏付けている。
長期にわたって他者貢献を行っている人々は、人生の満足度が高いと報告されている。
これは一時的な感情の高まりだけでなく、持続的な幸福感をもたらすことを示している。
また、文化的な側面も無視できない。
共同体主義的な文化では、他者との調和や協力が個人の幸福にとって重要な要素とされている。
これが、他者貢献が社会的に重視される理由の一つである。
こうした多面的な視点から見ると、他者貢献は単なる善行以上の深い意味を持つことがわかる。
生理的、心理的、そして社会的な利益を総合的に享受することで、私たちは個人としても社会としても、より豊かで幸福な状態を築くことができるのである。
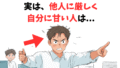
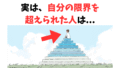
コメント