SNSを「見る専門」で利用する人は、自己開示欲求が比較的低い傾向にある。
心理学における自己開示理論によれば、人は他者との親密さを深めるために、自らの内面を意図的に語る行動を取る。
しかし、見る専門の人は、自分の情報を公開することに対してためらいがあり、他者からの評価や誤解を避ける傾向が強い。
その背景には、羞恥心や自己防衛意識、あるいは自己効力感の低さが存在していると考えられる。
自己効力感とは、「自分ならできる」という感覚であり、これが低いと、自ら発信する行動に対する自信が持てず、結果として沈黙する選択を取りがちである。
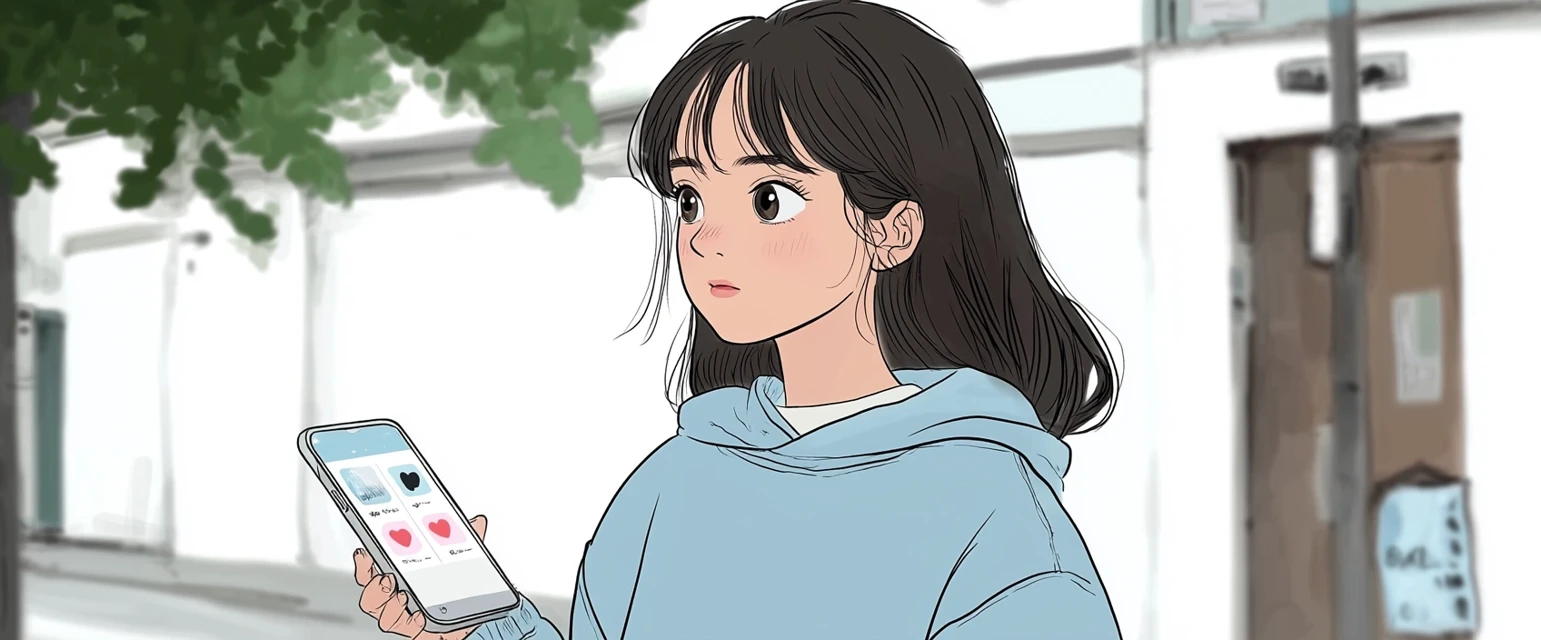
また、SNSを閲覧のみに使う人は、社会的比較の影響を受けやすい傾向もある。
他者の投稿は多くの場合、成功や幸福、承認欲求の充足といったポジティブな瞬間に偏っている。
こうした投稿ばかりを見続けると、自分とのギャップが強調され、自己評価が下がりやすくなる。
社会的比較理論においては、他者との比較によって自己像を確認する行動が人間には自然に備わっているが、閲覧主体のSNS利用では、比較の対象が常に「見栄えの良い他者」であるため、自尊心の低下や無力感を引き起こしやすい。

見る専門の人の多くは内向的な気質を持つともされる。
内向的な人は、広く浅い関係よりも、深く安定した関係を重視する傾向がある。
発信を伴うオンライン上のやりとりは、拡散される不確実性や他者からの反応への不安が伴うため、自己の境界を明確に保ちたい内向的な性格とは相性が悪い。
そのため、見る専門というスタイルは、自己を守るための適応的戦略とも言える。
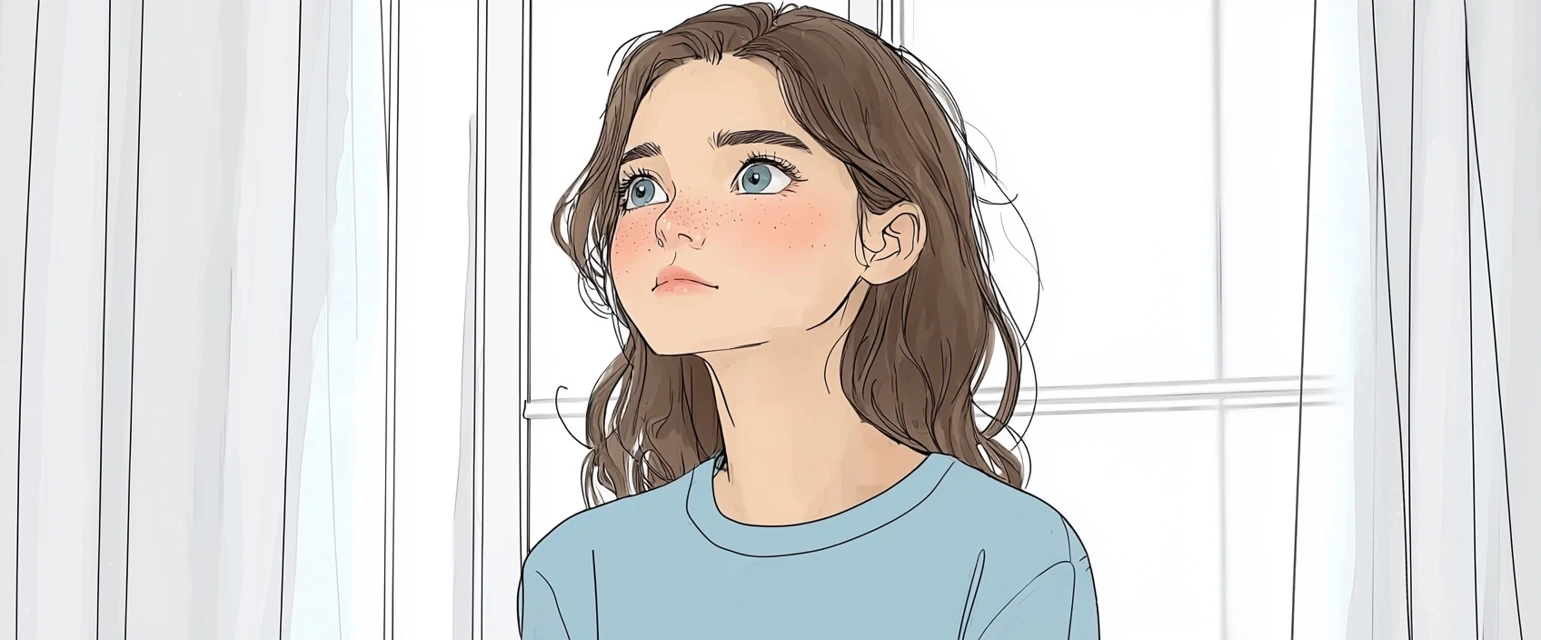
加えて、SNSを受動的に使う人は、FOMO(Fear of Missing Out=取り残される恐怖)にもさらされやすい。
発信はしないが、他人の動向を常に追いかけている状態は、「自分だけが何もしていない」「楽しめていない」といった感覚を強める。
FOMOは現代的なストレス要因のひとつであり、これに晒され続けることは、心理的な疲労や虚無感の蓄積につながる。
このように、SNSを「見るだけ」にとどめている人は、一見すると安定的で控えめな態度に見えるかもしれないが、その内面には自己防衛、低自己効力感、比較ストレス、FOMOといったさまざまな心理的メカニズムが絡み合っている。
発信しないことが必ずしも精神的安定を意味するわけではなく、むしろ静かな消耗を生んでいる可能性すらある。
SNSの利用は、外からは見えない心理状態を映す鏡でもあるため、「見る専門」という振る舞いの奥にも、繊細な内面の動きが潜んでいるのである。



コメント