人は日常会話の中で、無意識に同じ言葉を繰り返すことがある。
いわゆる「口ぐせ」と呼ばれるそれらの言葉には、話し手の性格や感情がにじみ出る。
しかし、中には本人が気づかぬうちに、周囲を不快にさせたり、信頼を損ねたりするものも含まれている。

たとえば、「でもさ」「いや、でも」といった言い回しは、相手の発言を否定する印象を与えることがある。
発した本人は反論のつもりがなくても、聞き手は「自分の意見を軽視された」と感じやすい。
会話はキャッチボールである以上、まずは相手の意見を受け止めてから、自分の考えを述べる姿勢が望ましい。
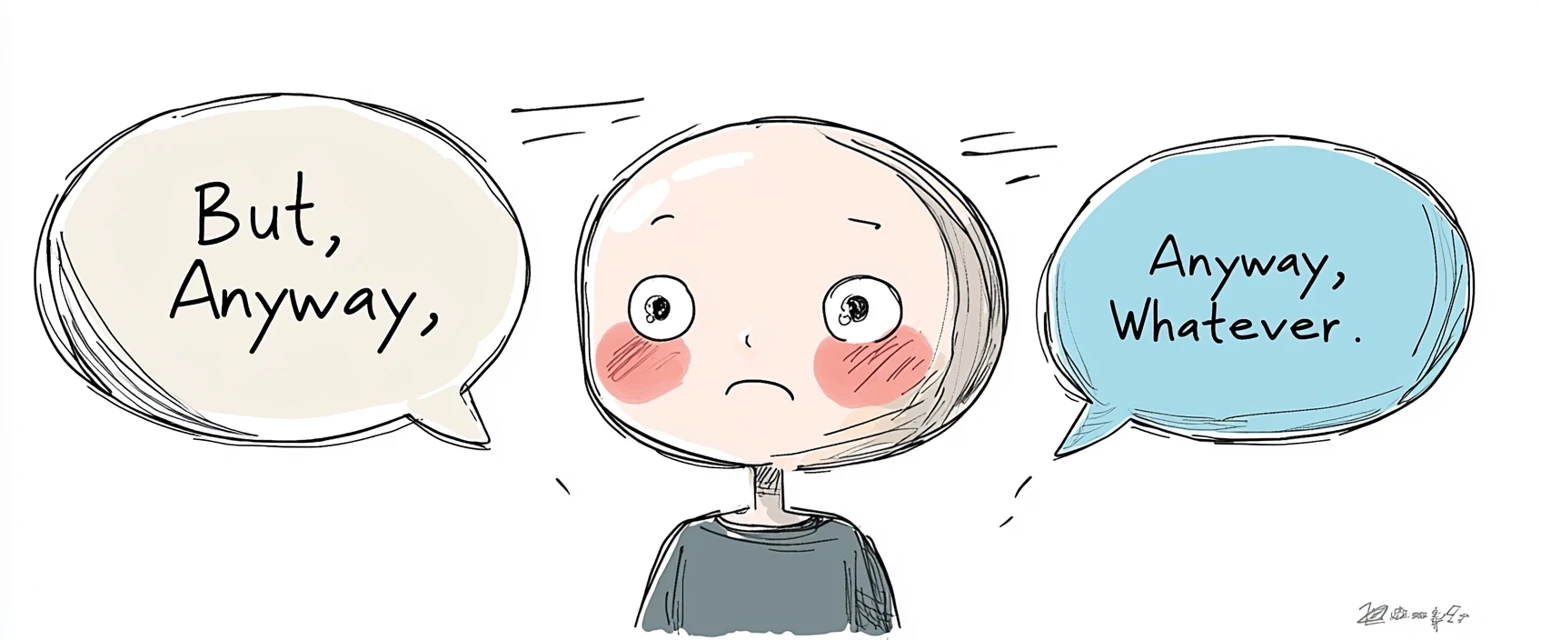
「どうせ」「無理でしょ」といった言葉も注意が必要である。
これは挑戦する前から諦めた態度を示す言葉であり、聞く側に無力感や重さを与えることがある。
自分を守るために出る言葉であっても、繰り返せば周囲のやる気を削ぎ、信頼を失う原因になりうる。
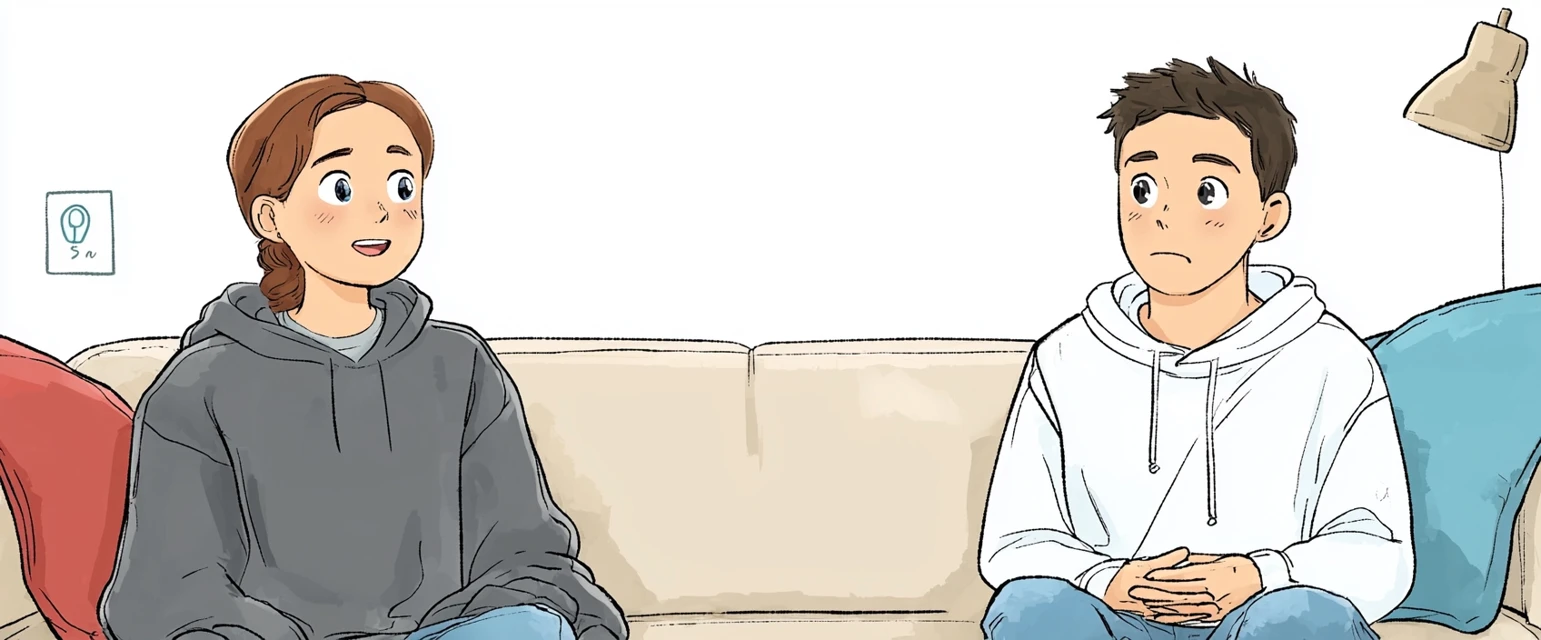
「っていうか」「てかさ」といった言葉は、会話の流れを強引に変える印象を与える。
主張を急ぐあまり、相手の話をさえぎるような形になりやすく、コミュニケーションが一方通行になりがちだ。
相手が話し終えるまで待つ余裕が、信頼関係の基本となる。
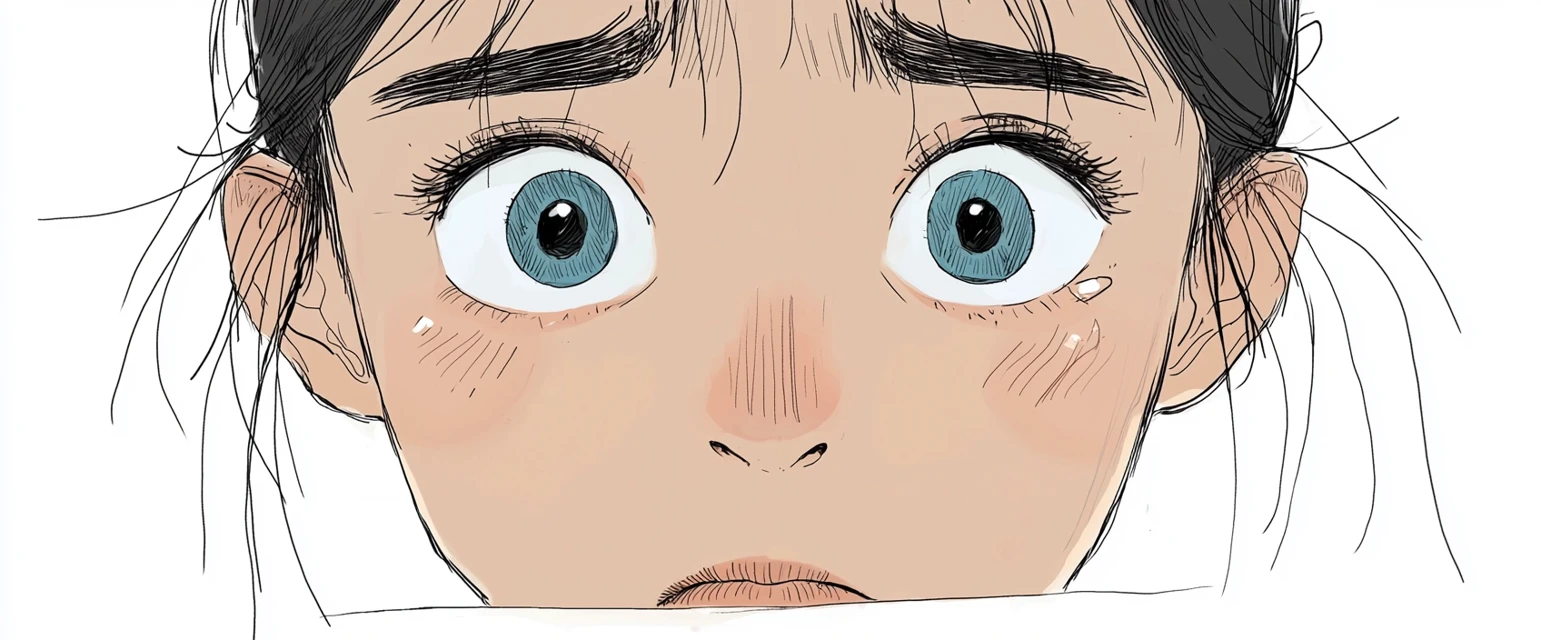
「別に」「なんでもいい」という言葉は、無関心や冷たさを感じさせる。
本人にとっては気遣いのつもりであっても、相手には「関心がない」「責任を取りたくない」と映ることがある。
意見をはっきり述べることが、むしろ相手への配慮になる場合もある。

「は?」「うざっ」といった短い攻撃的な表現は、瞬間的な不快感を強く残す。
これらは感情のコントロールが効かなくなった時に出やすいが、たった一言で関係が崩れることもある。
怒りを感じたときこそ、言葉を選ぶ意識が求められる。
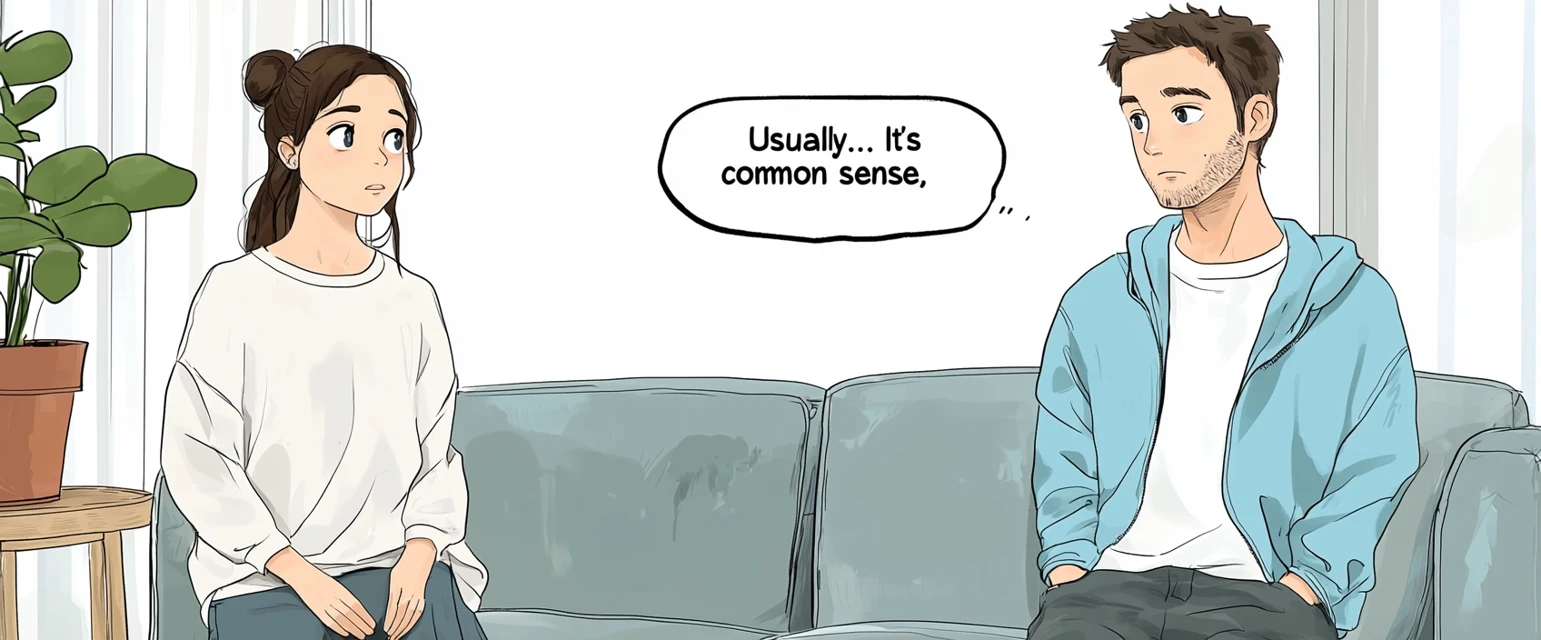
「普通は」「常識でしょ」という言葉も、人間関係を硬直させる要因になりうる。
何が「普通」であるかは人によって異なる。
自分の基準を押しつけるよりも、相手の視点に立ち、価値観の違いを前提に対話する姿勢が大切である。

「私なんて」「どうせ私なんか」といった自己卑下の言葉は、本人の内面の不安や自信のなさを表している。
しかし、それを繰り返すことで、周囲にフォローを求め続ける構図ができあがり、結果的に「重い」「扱いづらい」と距離を置かれてしまうこともある。
謙虚さと自己否定は似て非なるものだと理解したい。
これらの口ぐせは、性格の問題ではなく習慣の産物である。
したがって、意識的に言葉を見直すことで、関係性をより良い方向に変えることが可能である。
まずは自分の言葉に耳を傾けること。
変化はそこから始まる。



コメント