聞き流すのが得意な人は、ストレスに強い傾向があると言われている。
ただ「鈍感」なわけではなく、実は脳がうまく情報を選別し、感情を調整している可能性が高い。
人は日々、膨大な量の言葉や情報にさらされている。
すべてを真に受けていたら、脳が処理しきれず、心も疲れてしまう。
だからこそ、どれを気にして、どれを聞き流すかの選択が大切になる。
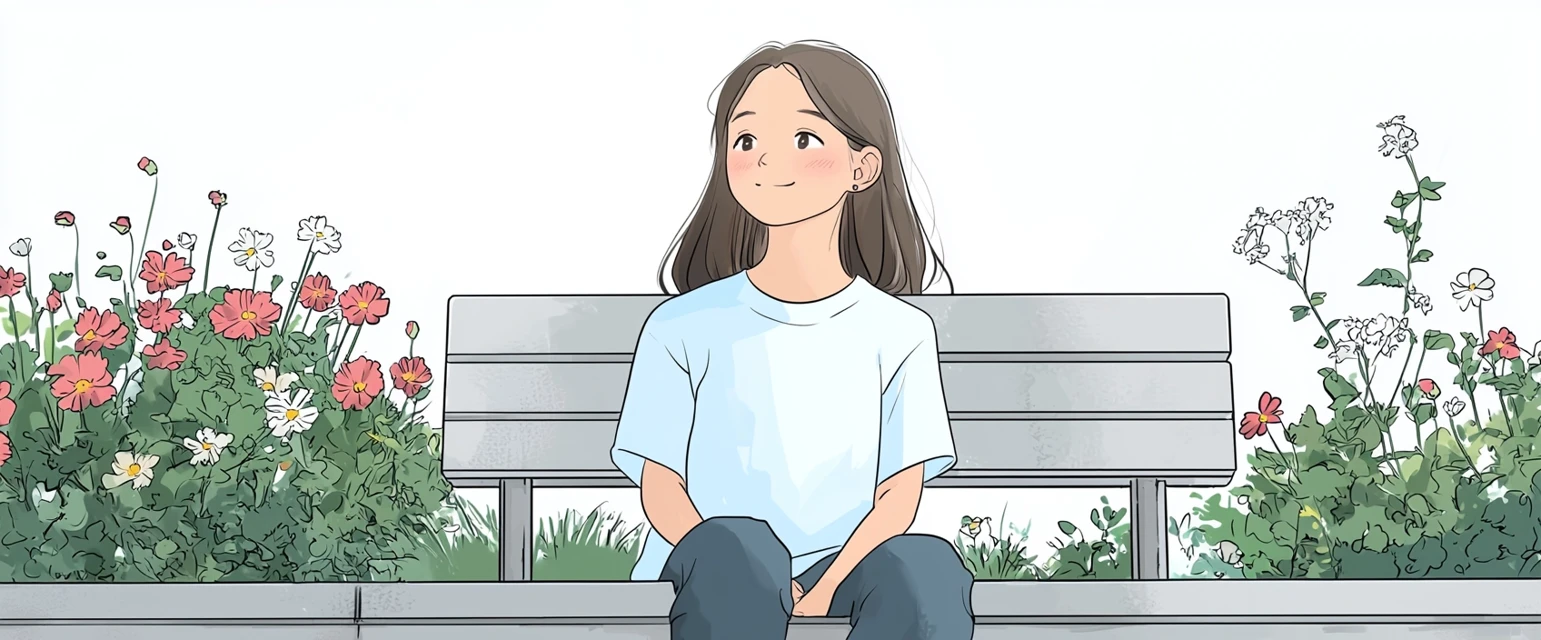
この「聞き流す力」は、脳の前頭前皮質という部分が担っている「実行機能」と深く関わっている。
実行機能とは、注意のコントロールや衝動の抑制、情報の整理などを司る働きのことだ。
聞き流せるということは、不要な情報を無意識に切り捨て、必要なことに集中できているという意味でもある。
これは、ただの無関心ではなく、自分にとって意味のない刺激を「気にしない」ことで、心の負担を軽くする仕組みでもある。

また、心理学には「感情調整」という概念がある。
これは、自分の感情の浮き沈みをコントロールする力のことだ。
聞き流すことができる人は、この感情調整力の中でも、「認知的再評価」と呼ばれるスキルをうまく使っている可能性がある。
たとえば、他人の嫌味を聞いても「まあ、あの人はいつもそうだし」と受け流せる人は、ストレスを感じにくい。
これは、その場の感情に反応するのではなく、心の中で状況を再解釈し、自分を守る考え方をしているからである。

こうした力は、人間関係にも良い影響を与える。
たとえば、職場や日常の中での無意味な言葉や愚痴を、適度に受け流すことができれば、余計な衝突を避けることができる。
しかも、表面上は相手に共感しているように振る舞いながら、心の中では必要以上に反応していない。
これは、一種の社会的スキルであり、「共感型スルー」とも呼べるテクニックである。
聞き流す力は、現代社会において重要な「心のフィルター」の役割を果たしている。
すべての情報に反応するのではなく、自分にとって意味のあるものだけを拾い上げる。
その積み重ねが、心の安定やストレス対処の力につながっていく。
聞き流すことができる人は、感情に振り回されず、冷静に物事を捉える力を持っていると言えるだろう。



コメント