本質を見抜く人は、物事の“奥”を見ようとする。
表面に出ている言葉や数字だけでは判断しない。
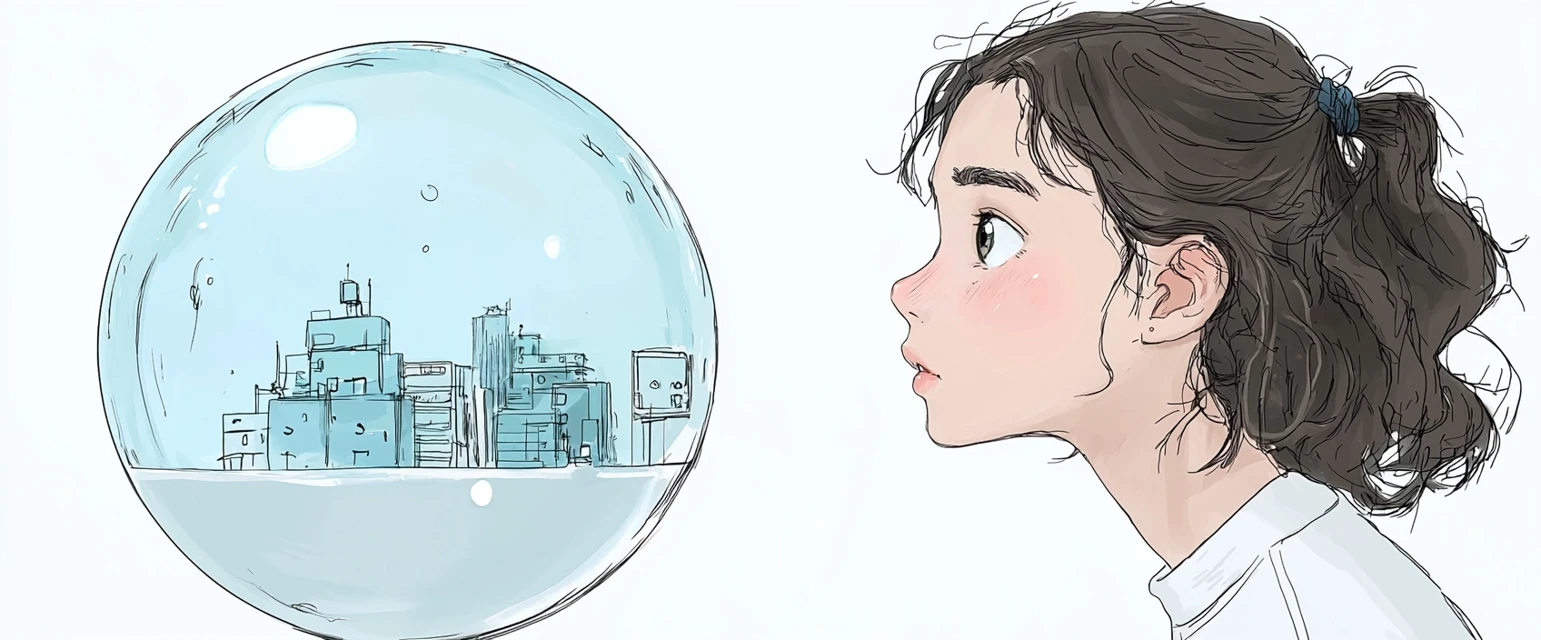
たとえば、会社の売上が下がったとき、「広告が足りない」「営業が弱い」と言うだけでは不十分だ。
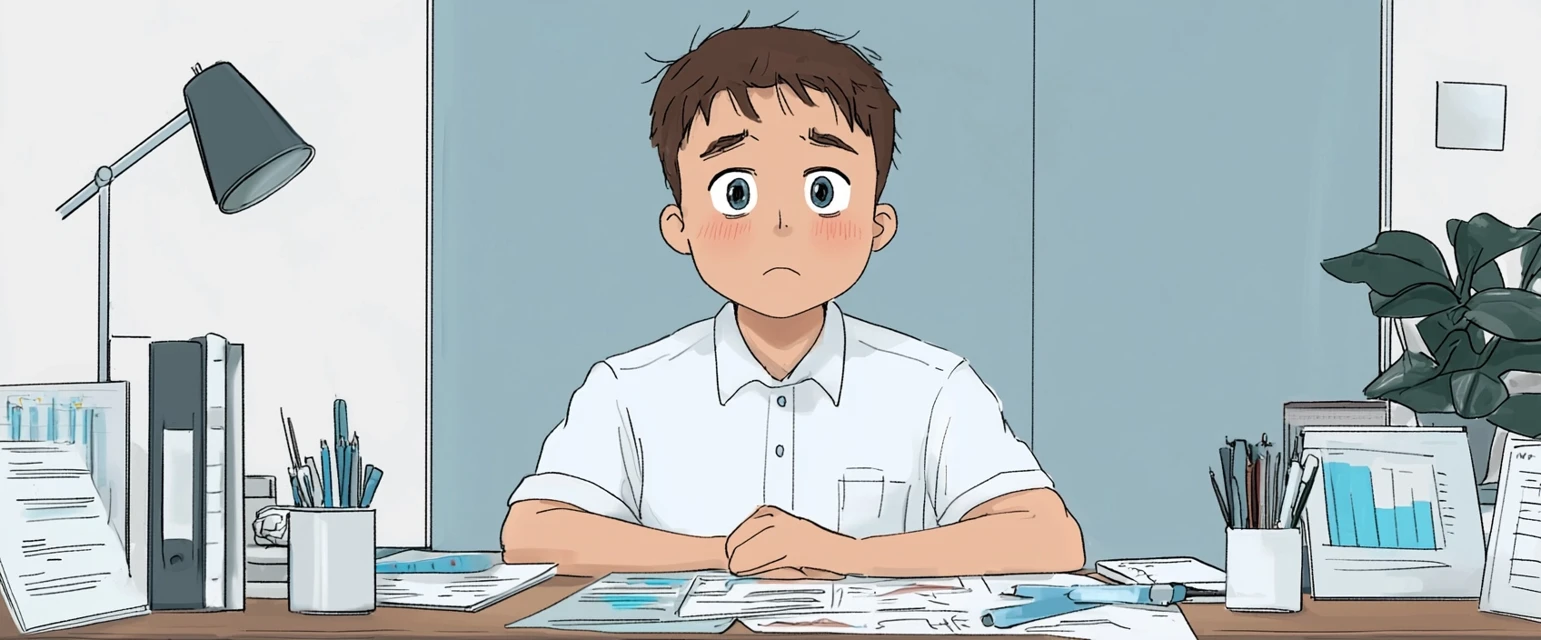
そういう人は、もっと深く考える。
「そもそも商品はお客さんの生活に合っているのか?」「社会の流れが変わったのでは?」
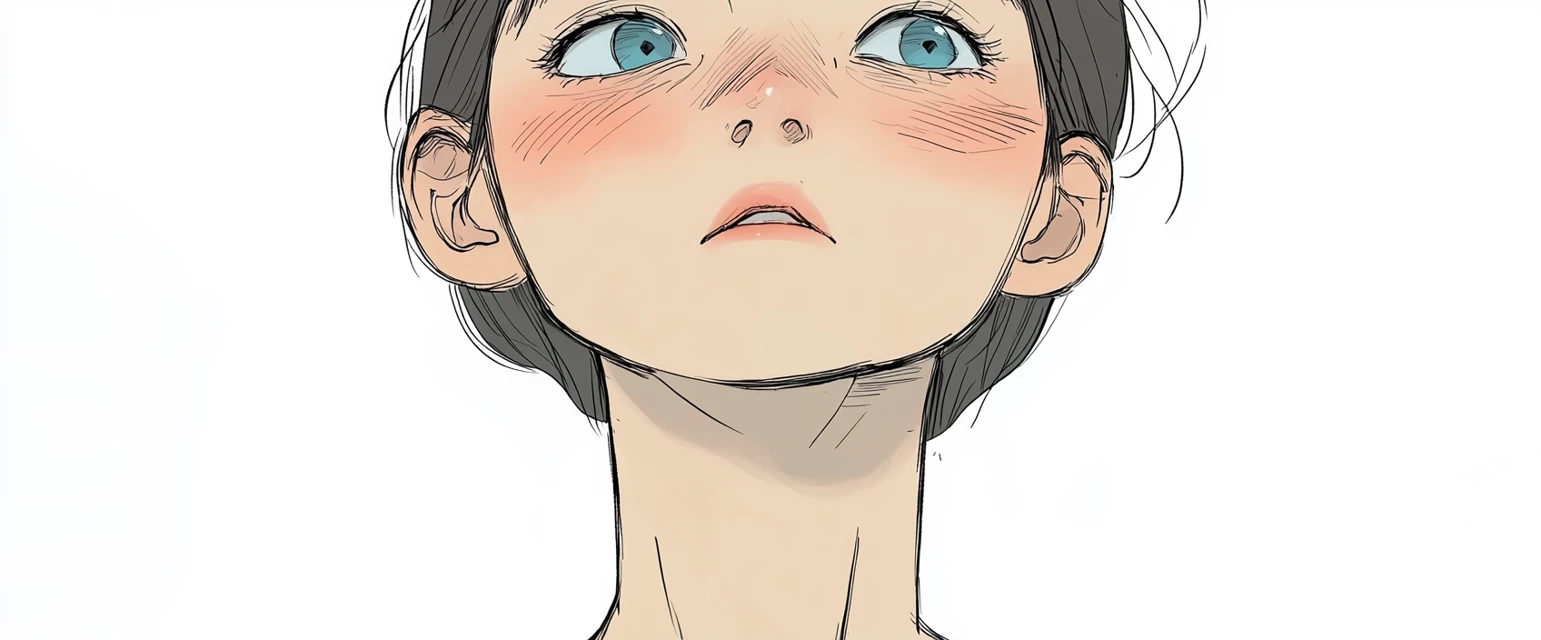
こうして、数字の背後にある原因や変化を探っていく。

人の気持ちに対しても同じだ。

誰かが不機嫌そうにしているとき、本質を見抜く人は「怒っている」だけで終わらせない。

「最近仕事が忙しすぎるのでは?」「評価されていないと感じているのでは?」と、表情の裏にある理由を探る。
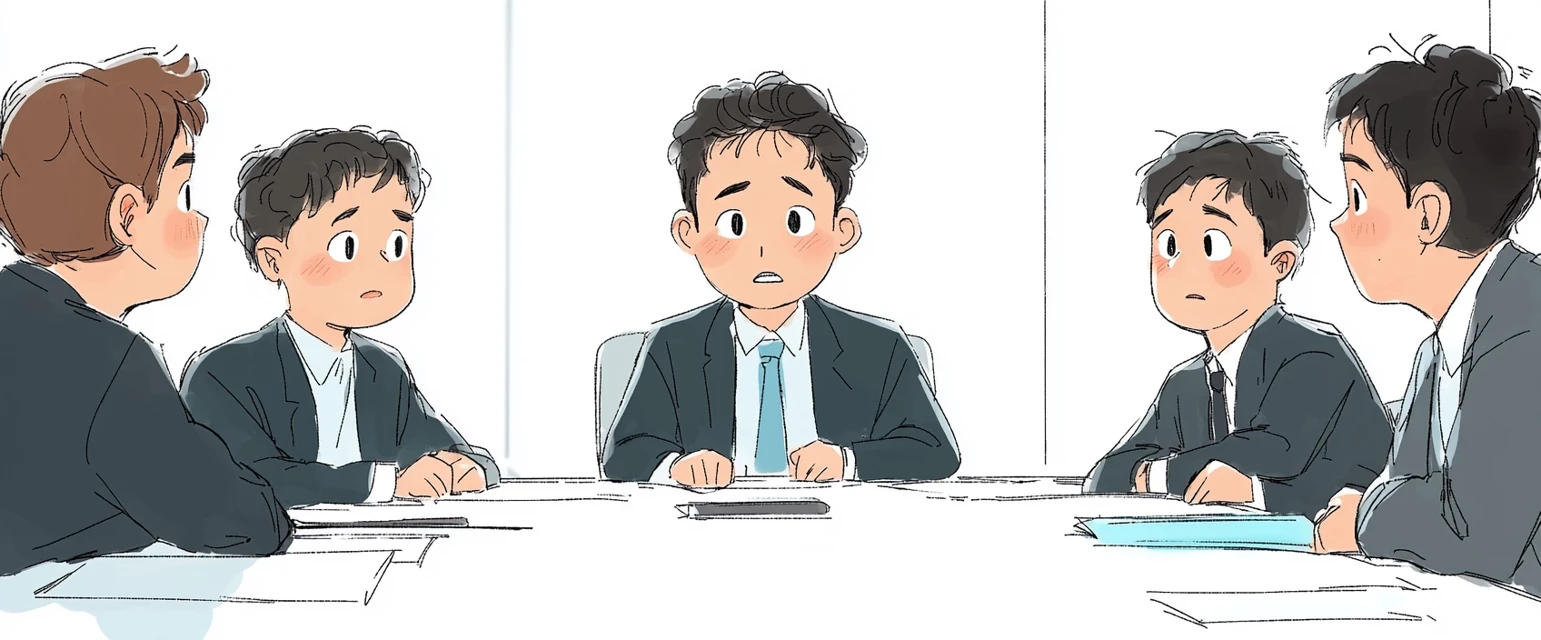
“怒り”という感情の下に、疲れや不安が隠れていることに気づこうとする。
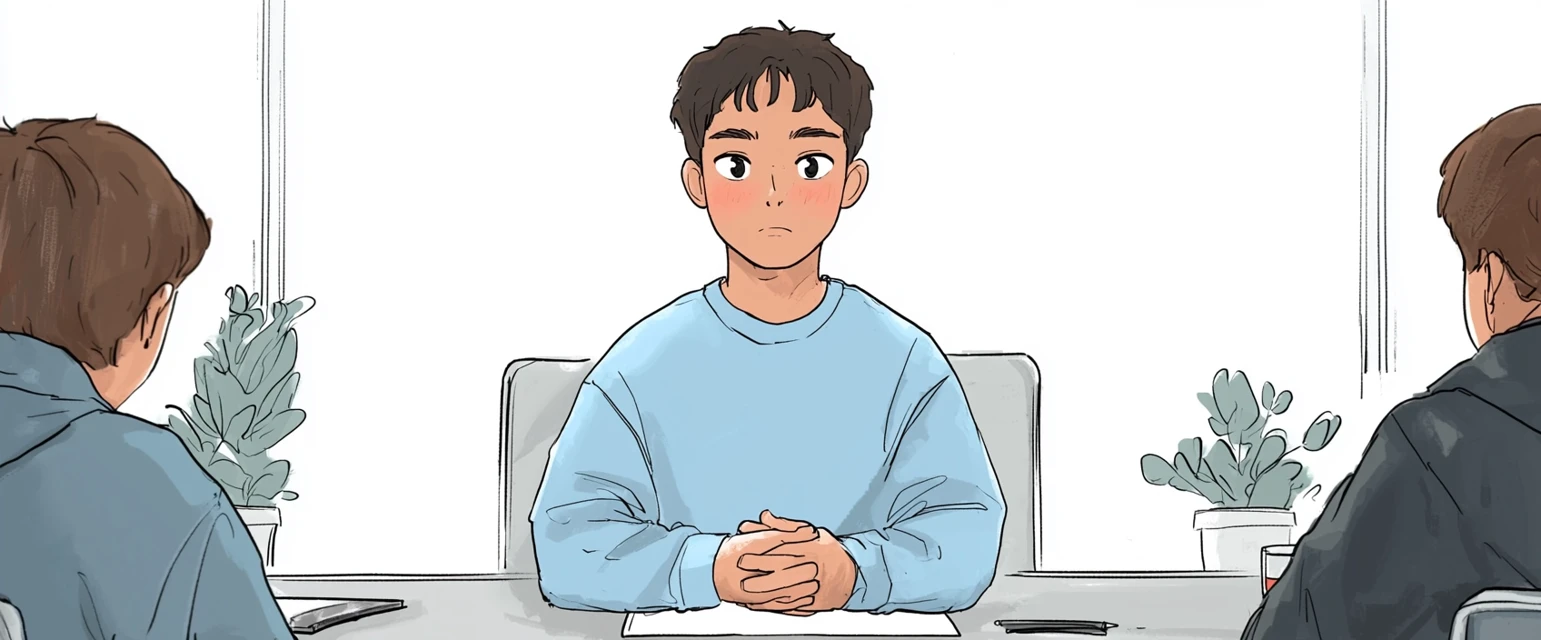
また、違和感を大事にする。

会議でみんなが賛成しているのに、なぜか空気が重い。
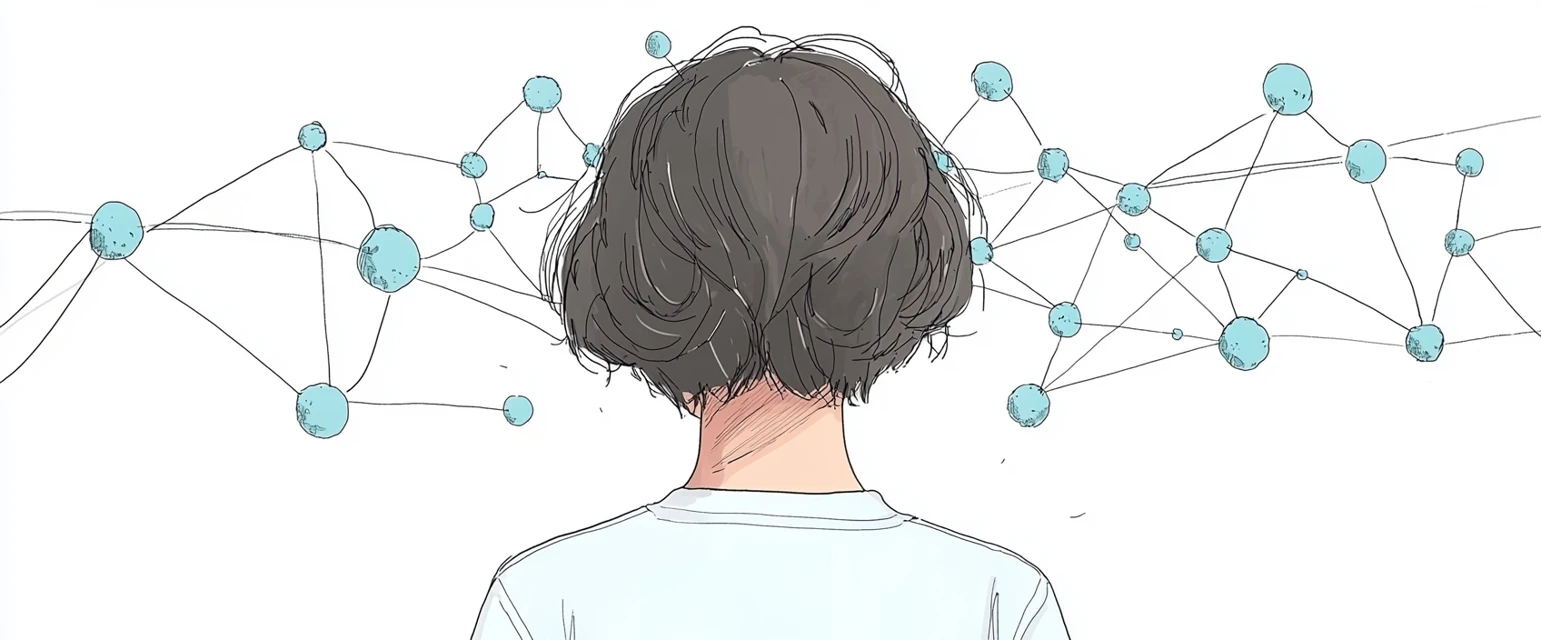
誰かが何も言わないまま黙っている。
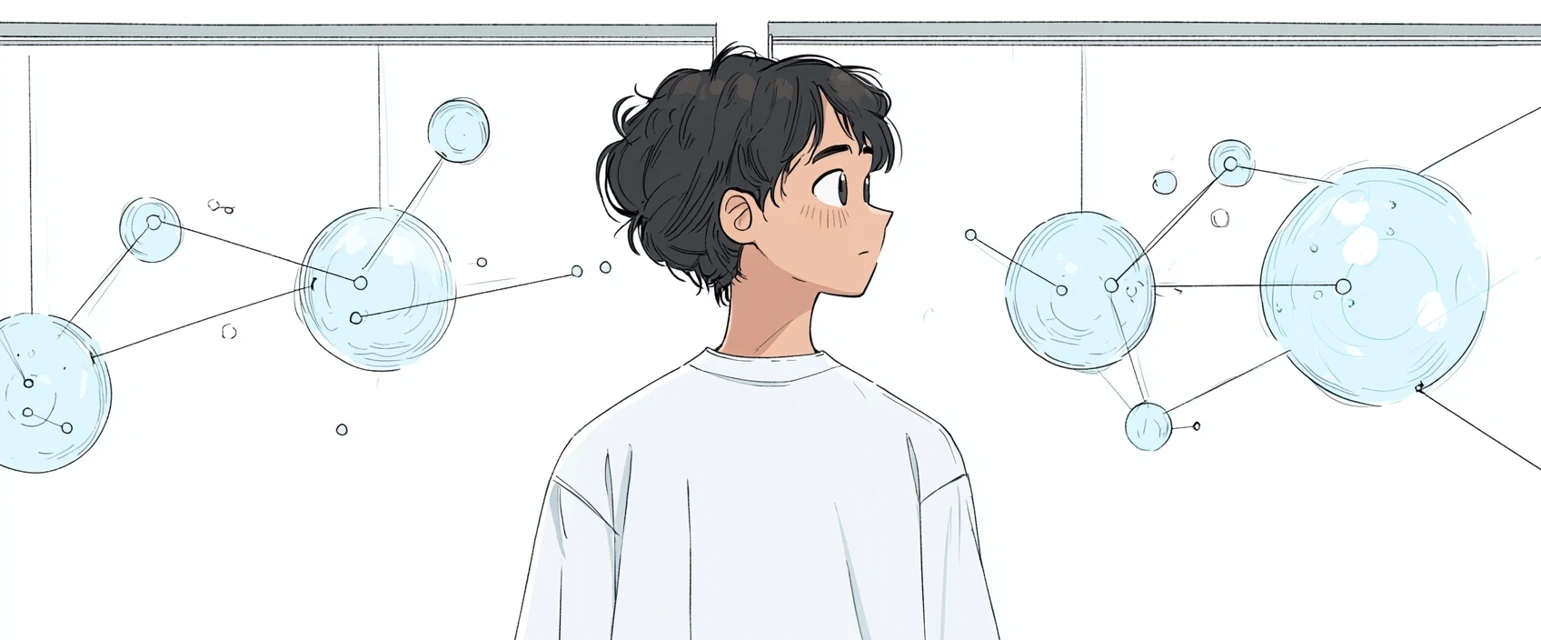
そういう場面で、本質を見抜く人は止まる。
「みんな本当に納得してるのか?」「誰か言いにくいことを我慢していないか?」

違和感は、言葉にできない“サイン”である。

本質を見抜く人は、物事の構造に注目する。

たとえば、学校でいじめが起きたとき、「加害者が悪い」と言うだけでは足りない。

「なぜそういう関係が生まれたのか?」「先生やクラスの空気はどうだったか?」
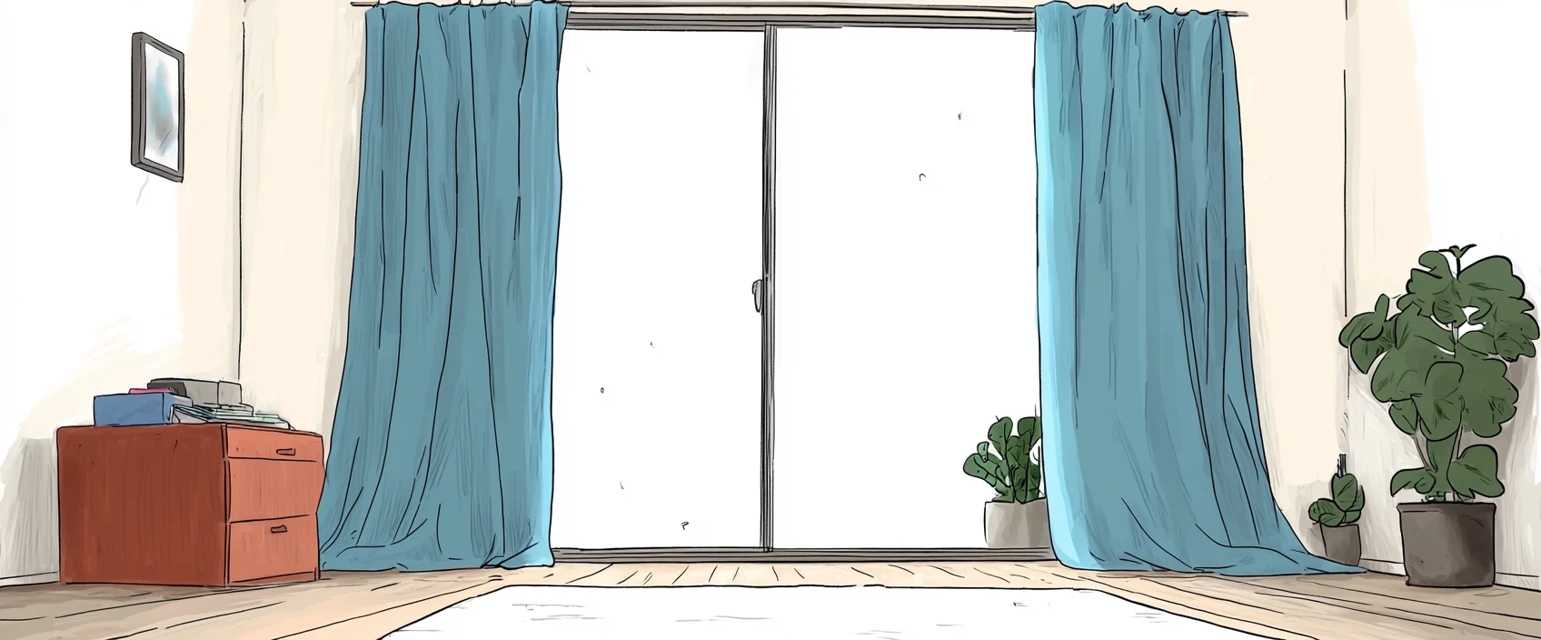
一人の行動ではなく、全体の流れや仕組みを見る。
これが“構造を見る”ということだ。

そして、何よりも自分自身の心も見つめる。
誰かにイライラしたとき、そのまま怒ったり、悪く思ったりしない。
「なぜ自分はここまで反応しているのか?」と内側を見つめる。
自分の思い込みや感情のクセに気づく力は、他人を見る目にもつながる。
本質を見抜く人は、「どうすれば?」と考える前に「なぜそうなっているのか?」と問う。
「売れるには?」ではなく、「なぜ人はこの商品を必要とするのか?」
「どうすればあの人を変えられるか?」ではなく、「なぜ自分はその人を変えたいと思っているのか?」
問いの深さが、見えるものを変える。
本質を見るとは、目立つものに飛びつかず、静かに、深く、考えることである。
情報ではなく背景を。
言葉ではなく沈黙を。
結論ではなく問いを。
それが、見逃されがちな真実に気づく力になる。



コメント