家族の期待は、ときに力になるが、過度になると心に重くのしかかってくる。
「あなたならできる」「もっと頑張れるはず」といった言葉が励ましになる一方で、無意識のうちに「今のままでは足りない」と感じてしまうこともある。

こうした状況は、心理学では「ピグマリオン効果」と呼ばれている。
他人から期待されることで能力が引き出されることがある一方で、過剰な期待はプレッシャーとなり、かえって本来の力を発揮できなくなることもある。
これが「ゴーレム効果」と呼ばれる現象だ。
要するに、期待には良い面と悪い面がある。
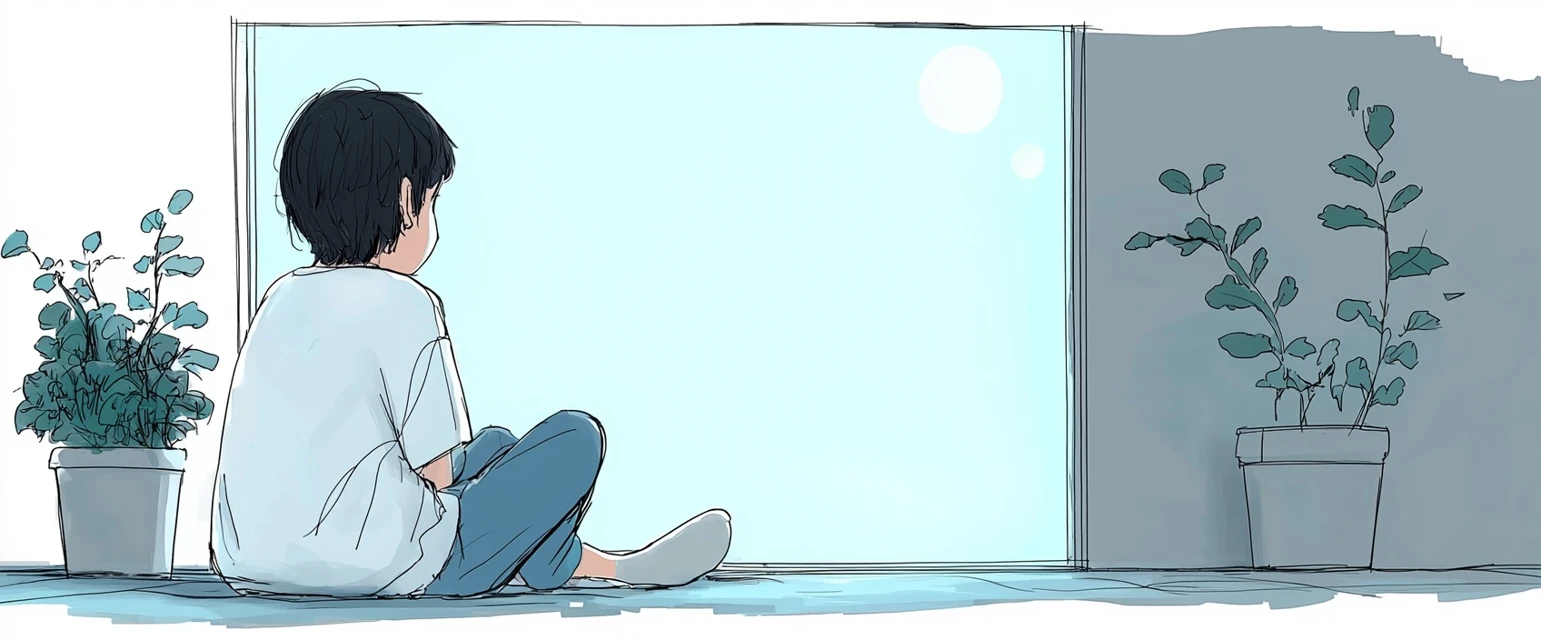
脳の働きにもそれは表れている。
やる気や楽しさを感じるときには、脳内でドーパミンが分泌されるが、強い不安や恐れを感じたときには扁桃体が反応し、ストレス状態に陥る。
これが続くと、集中力が落ちたり、心身に不調をきたす原因になる。
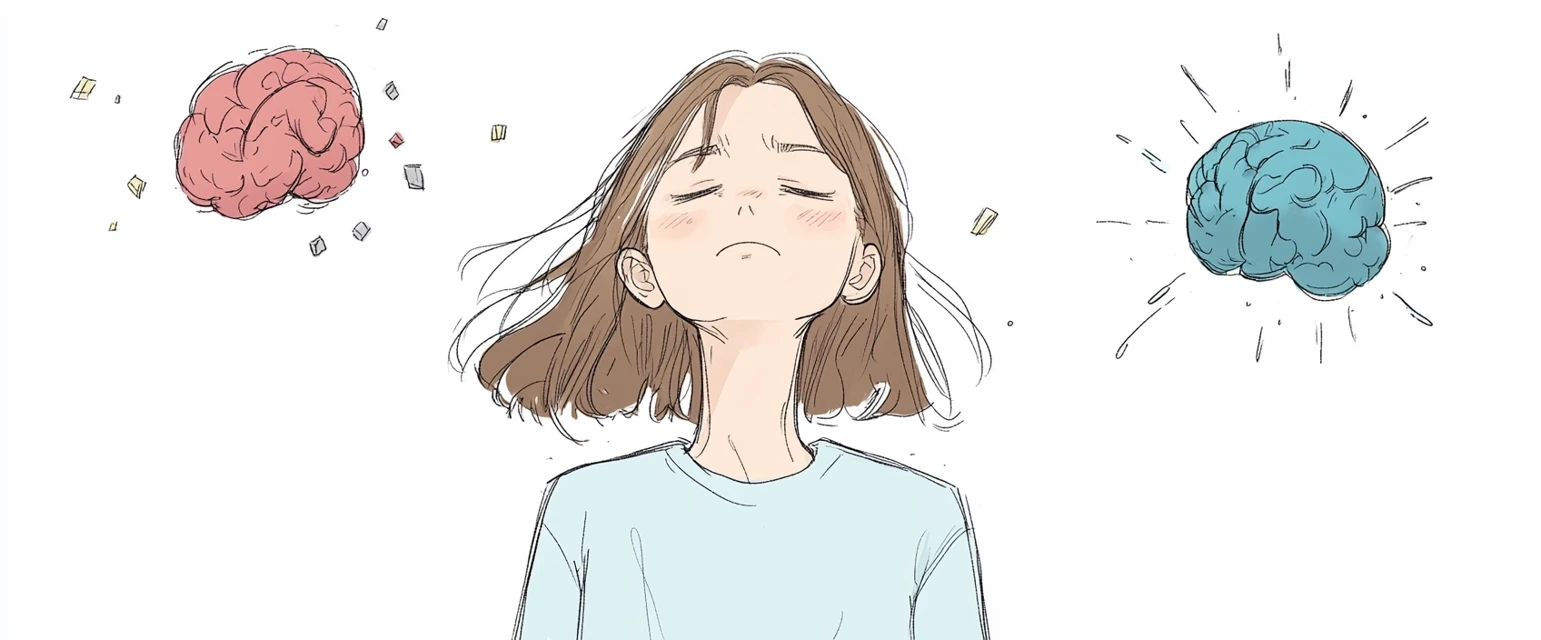
日本の文化も関係している。
多くの人が「親の言うことには従うべき」「家族の期待に応えるのが立派だ」という価値観の中で育ってきた。
そのため、たとえ自分の本音とは違っていても、期待に沿うことを優先してしまいがちである。
もちろん、家族の願いは善意であることが多い。
しかし、それが本人の幸せとズレていると、次第に生きづらさを感じるようになる。
では、どうすれば家族の期待と自分の気持ちの間で折り合いをつけることができるのか。
ここからは実践的な方法を紹介する。

まず大切なのは、自分の本音を明確にすることである。
静かな時間をとって、自分が何を大切にしたいのか、どんな生き方をしたいのかを考えてみる。
他人の望む生き方ではなく、自分にとって意味のある道は何かを言葉にしてみると、心が整理されやすい。
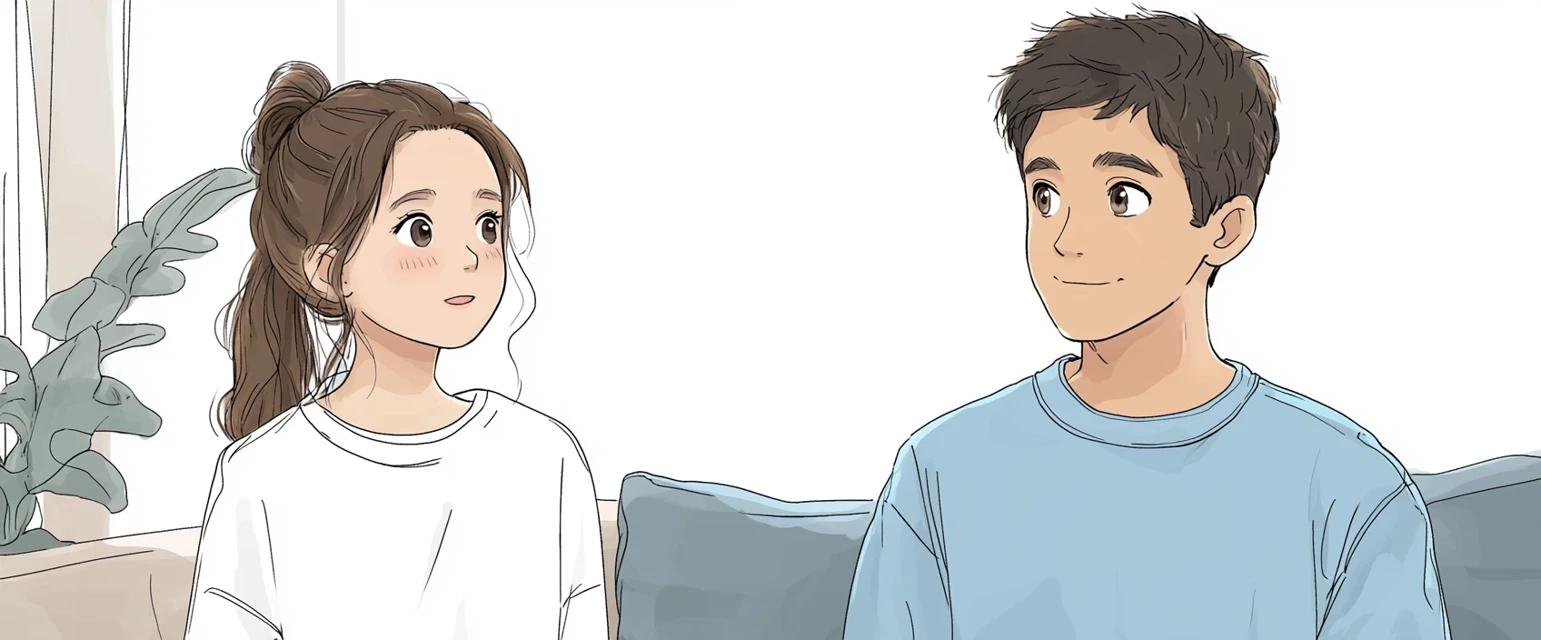
次に、家族との対話を試みることだ。
反発するのではなく、「どうしてその進路をすすめてくれるの?」「それを望む理由を教えてほしい」と、相手の気持ちを聞く姿勢で話すと、思いがけない本音や背景が見えてくることがある。
親もまた、不安や願いを抱えているのだと分かると、ただの押しつけではなく、対等な会話が生まれやすくなる。

さらに、自分なりの小さな目標を立てて、達成する経験を積み重ねることも効果的である。
他人に認められなくても、自分で「やってよかった」と感じられることを選び、それを少しずつ形にしていくことで、自信が育っていく。
大きな成功ではなくても、「これは自分で決めてやり遂げた」という感覚が、家族の期待から自分を切り離す力になってくれる。
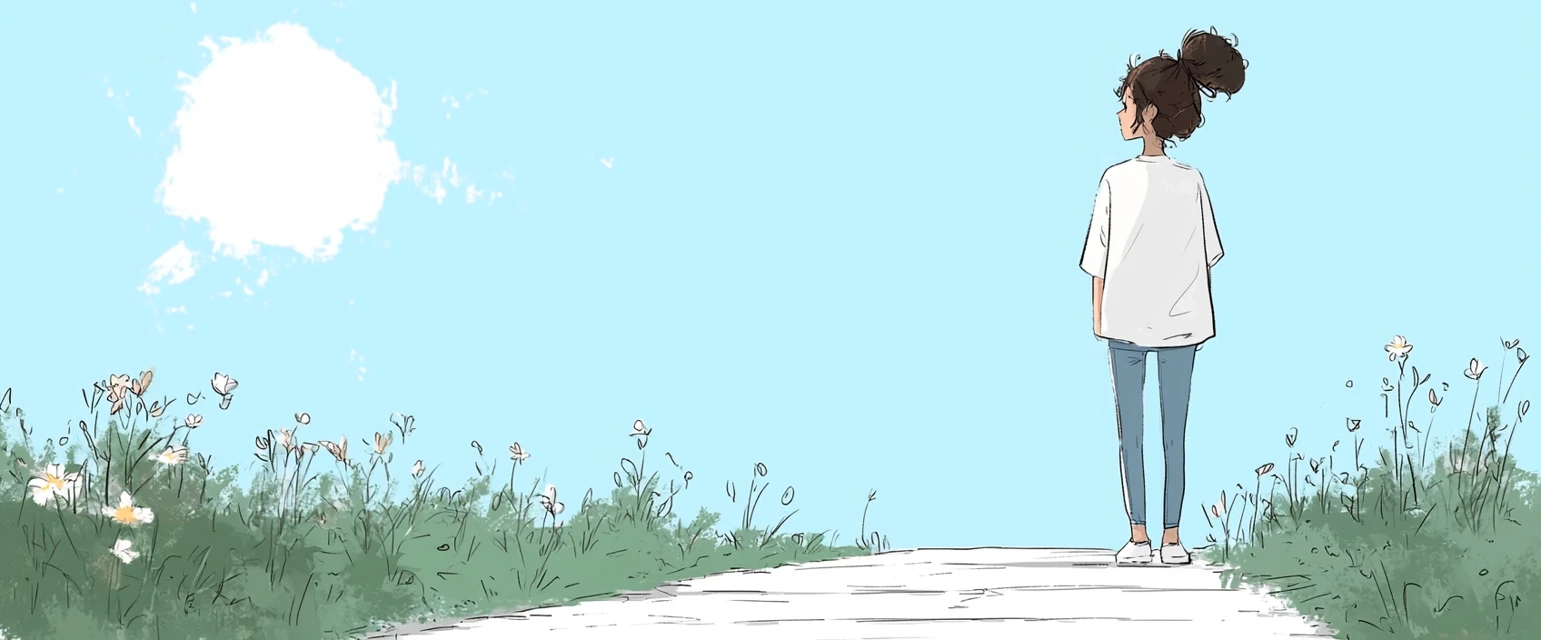
また、どうしても重圧に耐えられないときには、信頼できる第三者に話を聞いてもらうのも良い方法である。
友人、先生、カウンセラーなど、家族とは別の視点を持った人に相談することで、新しい気づきが得られることもある。
家族の期待に応えることそのものは悪いことではない。
だが、それが自分の気持ちを無視したものであれば、どこかで心が苦しくなってしまう。
大切なのは、他人の理想を生きるのではなく、自分の意思で選んだ道を歩くことだ。
その姿を見せることこそ、最終的には家族の理解を得る近道にもなる。


コメント