多少の体調不良なら無理してでも動こうとする人には、いくつかの心理的傾向が見られる。
まず一つ目に、病人としてふるまうことへの抵抗がある場合が多い。
本来、体調が悪いときには「休む」「人に助けを求める」といった行動は当然のことであり、社会的にも認められている。
しかし、こうした行動を「甘え」や「怠け」と捉え、自分に許せない人も存在する。
こうした人は、幼い頃から他人に頼ることを避け、常に周囲に気を配りながら生きてきた傾向があり、自分の欲求や不調を後回しにする「過剰適応」と呼ばれる状態にあることが多い。

また、自分には何があってもやり遂げられるという強い自信、いわゆる自己効力感が強すぎる場合にも、無理をしてしまうことがある。
特に、完璧主義の傾向がある人は、「できない自分には価値がない」と感じてしまい、少しの不調でも休むことに強い抵抗を覚える。
これは意識的というよりも、「周囲からどう見られるか」「評価が落ちるのではないか」という不安が無意識に行動を左右していることが多い。

さらに、身体の不調や感情の変化に鈍感な人も、体調不良を見逃しがちである。
これは「アレキシサイミア」と呼ばれる特性で、身体の不快感を感じても、それをうまく認識したり言語化したりできないことが特徴である。
例えば、強いストレスが原因で頭痛や胃痛が起きていても、「ただの疲れ」や「気のせい」と受け止めてしまい、必要な休息を取らずに働き続けてしまう。

その背景には、承認欲求の影響もある。
「体調が悪いのにがんばっている自分」を見せることで、周囲から感謝や評価を得ようとする心理が働く。
これは決して意図的なアピールではなく、幼少期から「役に立つことでしか認められない」と学んできた人に多く見られる傾向である。
自分の体調よりも、他人にどう見られるかを優先してしまうため、無理をしてでも動こうとする。
さらに、働きすぎが美徳とされる文化的背景も影響している。
「多少の不調で休むのは甘え」といった価値観や、「体調管理も仕事のうち」という言説が、無理を正当化する空気を生んでいる。
こうした環境の中で生活していると、自分が本当に休むべきかどうかを冷静に判断することが難しくなる。
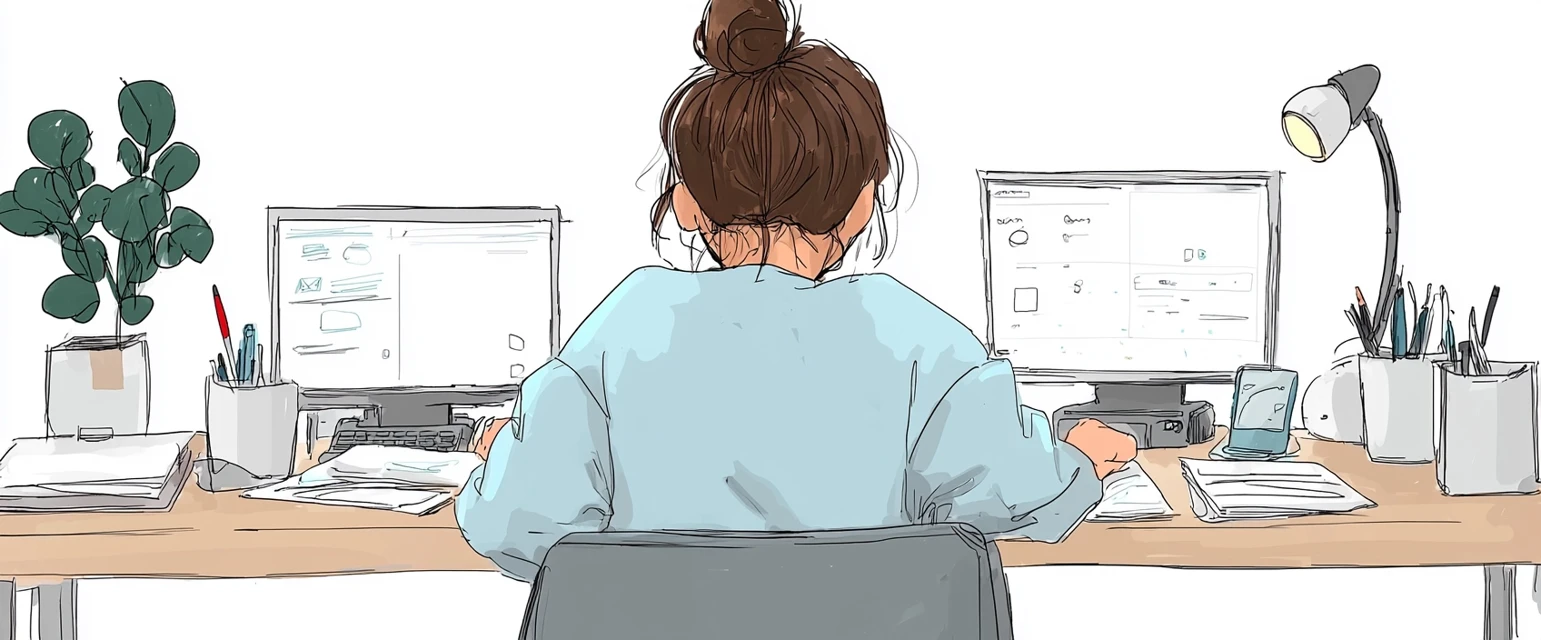
このように、「少しぐらいなら大丈夫」と思って無理を重ねる人には、感情の抑圧、自己評価のゆがみ、文化的プレッシャーなど、さまざまな心理的要因が複雑に絡み合っている。
その根底には、「人に頼ることへの不安」や「弱さを見せることへの恐れ」があり、それが日常のささいな選択にも影響を及ぼしている。
自分に対してもう少し寛容になり、「無理をしないこと」もまた強さの一つであると認識することが、心と体の健康を保つ第一歩になる。
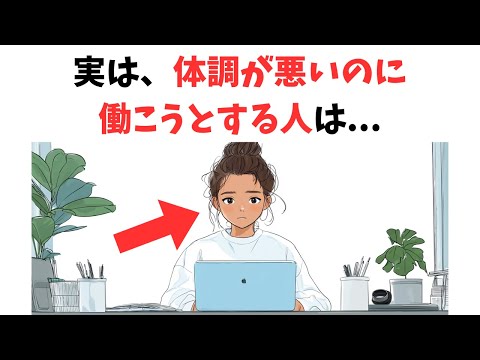


コメント