自己調整学習とは、まるで自分自身が「教師」となって学びを導くような方法である。
誰もが一度は、何かを学ぶ過程でつまずき、どうすればもっと効果的に学べるのかと悩んだことがあるだろう。
この学びの旅をよりスムーズに進めるための鍵が、自己調整学習にある。

この学習方法は、まず初めに計画を立てることから始まる。
目標を設定することで、自分がどこに向かっているのかを明確にし、道筋を描くことができる。
例えば、「次の試験までにこの教科書をすべて理解する」といった具体的な目標を立てることで、学習の方向性がはっきりとする。
次に、実行段階では、自分の学習の進捗を監視し、必要に応じて戦略を修正する。
このときに重要なのがメタ認知のスキルである。
自分自身を客観的に見つめ、今どれくらい理解できているのか、どこでつまずいているのかを把握する力が求められる。
例えば、新しい概念を理解するために、別の参考書を使ってみたり、友人とディスカッションをしてみたりと、自らの学び方を柔軟に変えることができる。
そして、反省段階では、学習の成果を振り返り、次のステップに活かす。
自己評価を行い、何がうまくいったのか、どこを改善すべきかを考えることで、次回の学習がさらに効果的になる。
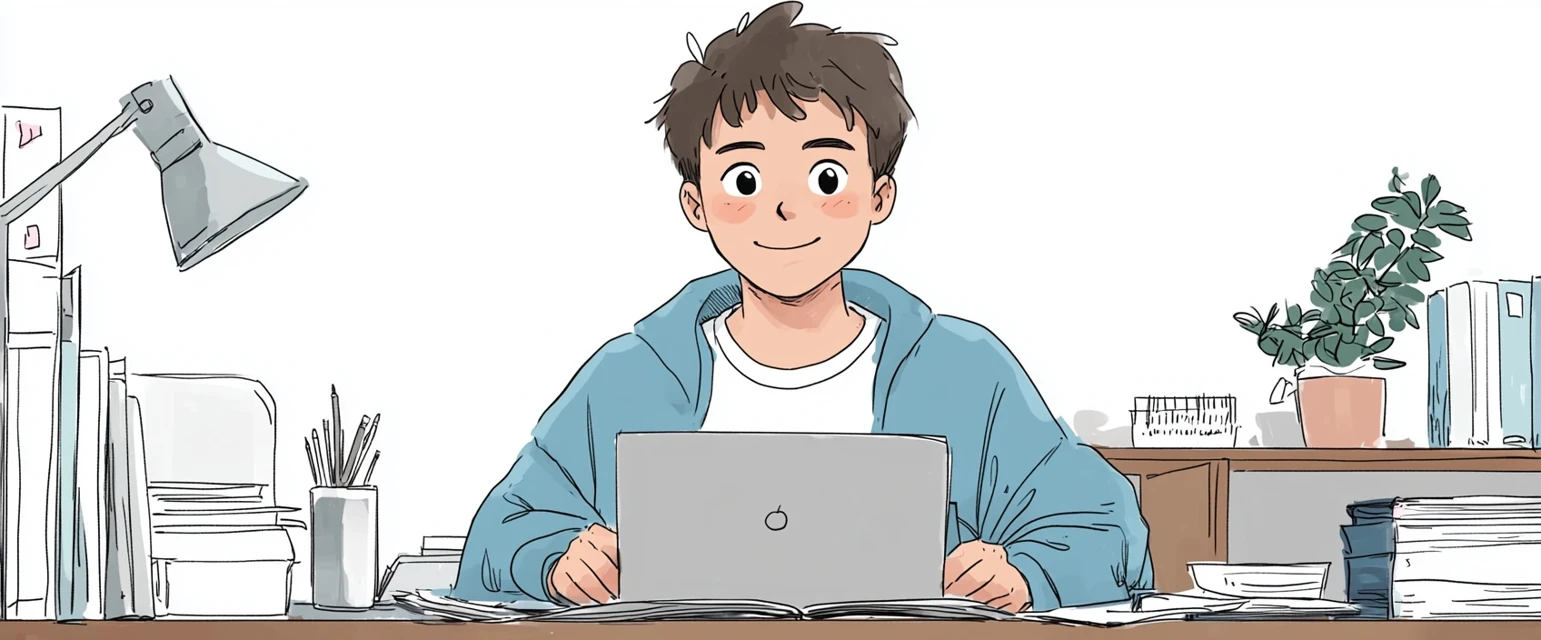
自己調整学習を理解する上で、いくつかの理論が役立つ。
社会認知理論では、自己効力感が学習の成功に大きく影響するとされている。
自己効力感とは「自分ならできる」という信念であり、これが強いほど、学習者は困難に直面しても諦めずに挑戦を続けることができる。
また、自己決定理論では、内発的動機づけが重要視される。
学ぶこと自体に楽しさや興味を感じることで、学習はより持続可能なものになる。
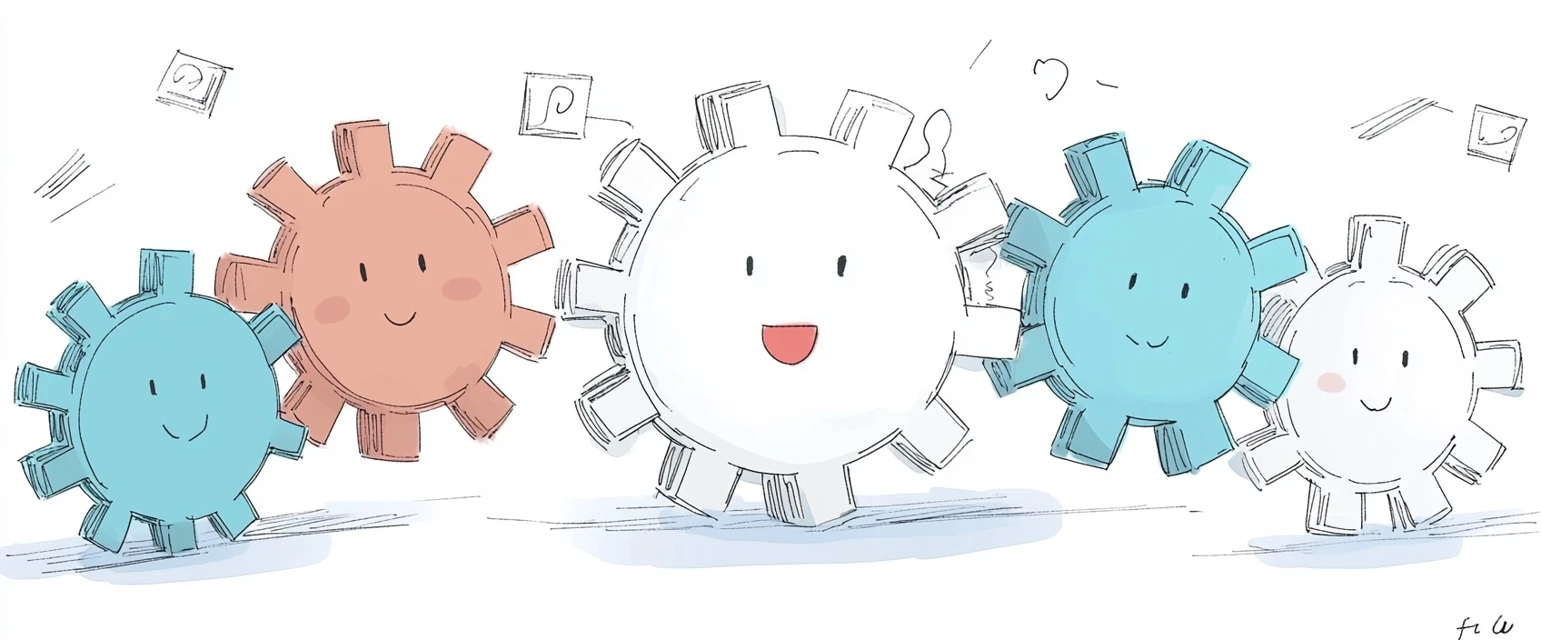
自己調整学習を進めるためには、いくつかの戦略がある。
リソース管理では、時間や環境を効率的に利用することが求められる。
例えば、静かな場所を選び、学習に必要な資料を事前に準備しておくことが重要である。
また、要約やマインドマップの作成などの学習戦略を活用することで、情報を整理し、理解を深めることができる。
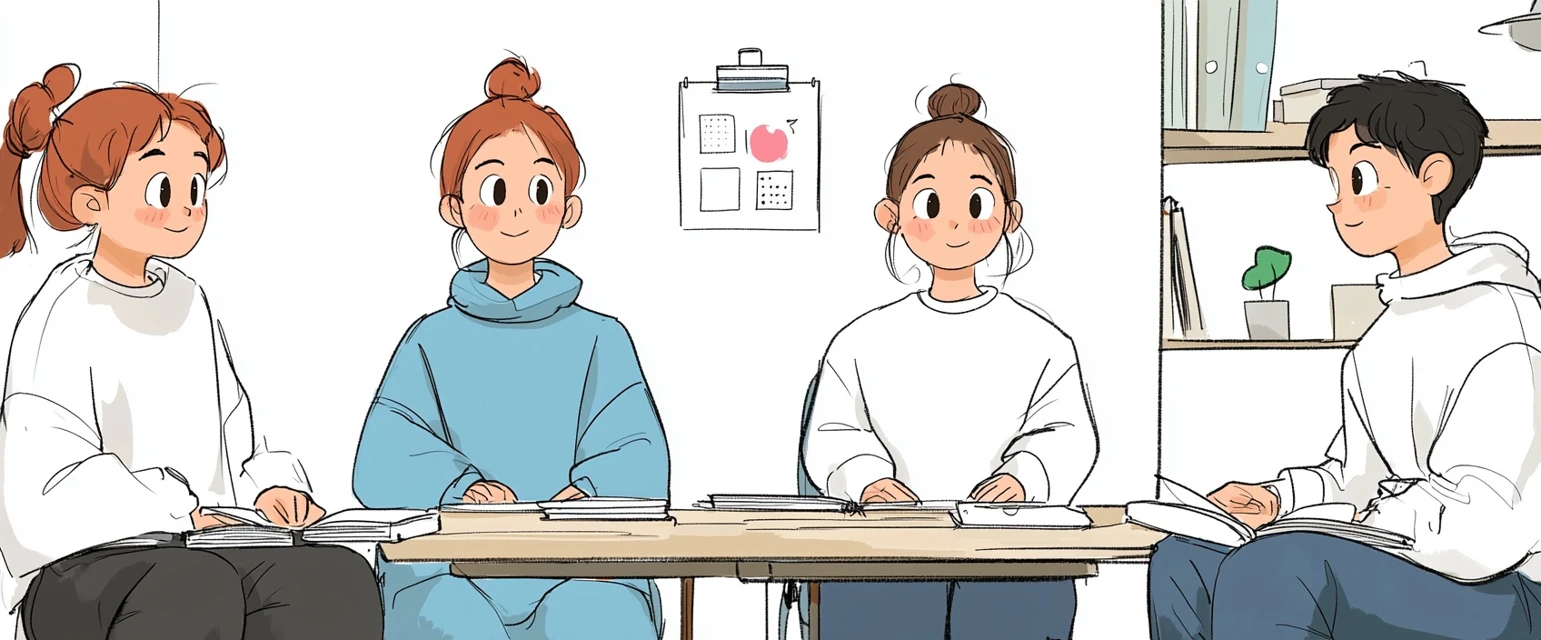
しかし、自己調整学習には課題もある。
過負荷やモチベーションの維持が難しくなることがあるため、無理のない計画を立て、小さな成功体験を積むことが大切である。
これにより、自己効力感が高まり、さらなる学習意欲が生まれる。

自己調整学習は、特にオンライン学習やリモート教育の場面で大きな力を発揮する。
自分自身で学びを管理する力を身につけることで、どんな状況でも効果的に学ぶことができる。
この方法を実践することで、生涯にわたって学び続ける力を向上させ、より豊かな人生を送ることができるのである。
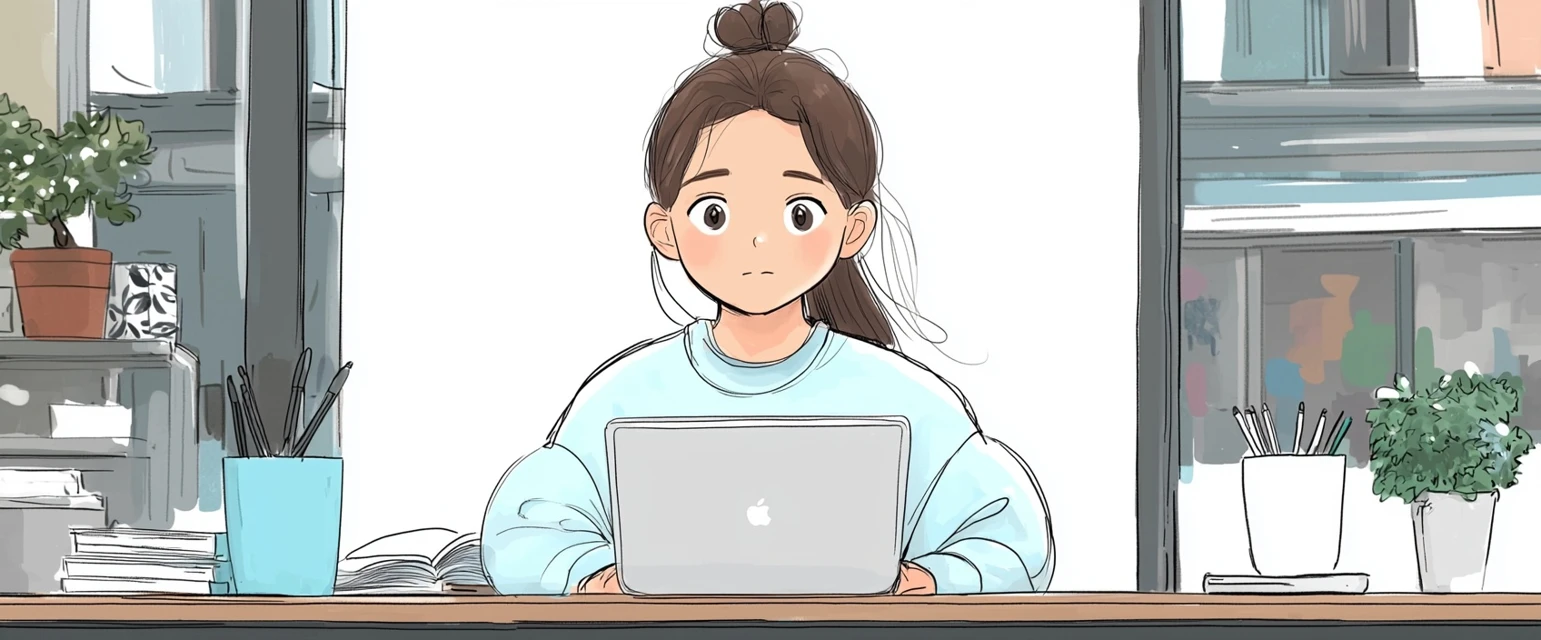
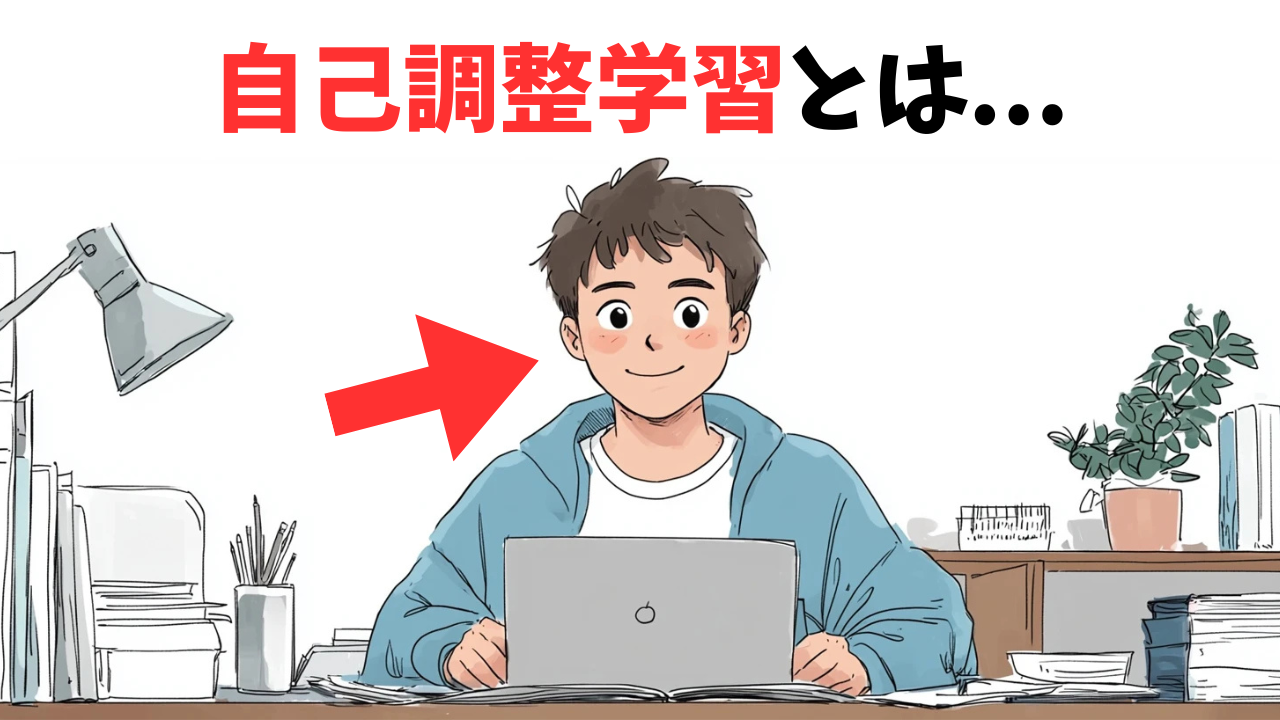

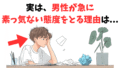
コメント