交渉が苦手な人でも、いくつかの心理テクニックを知っておくことで、落ち着いて会話を進めることができるようになる。
重要なのは、「相手を言い負かすこと」ではなく、「相手と同じ方向を向くこと」である。
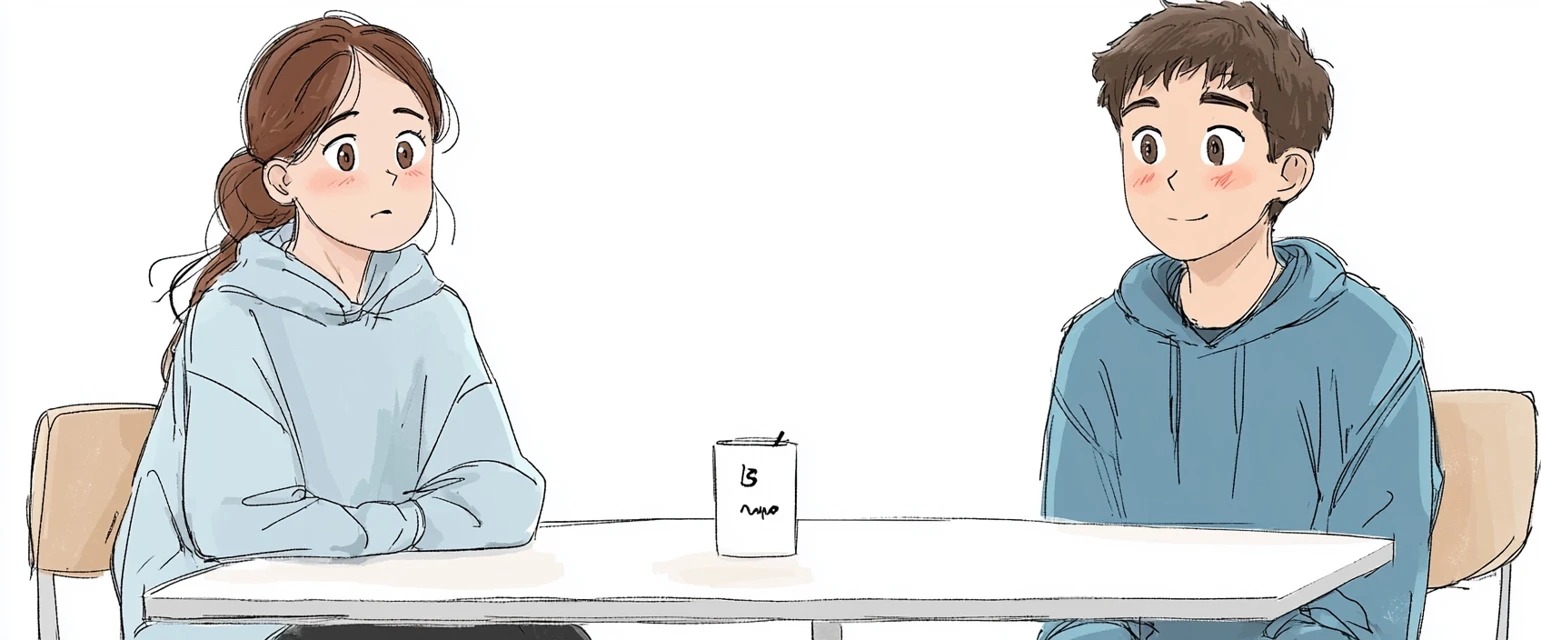
まず使いやすいのが「YESセット」と呼ばれる話法である。
人は連続して「はい」と答えていると、その流れで次の質問にもつい「はい」と言ってしまいやすくなる。
例えば、「最近忙しいですよね」「天気も不安定ですね」「できるだけスムーズに進めたいですよね」といった同意しやすい話題を並べたあとに、本題を切り出すと、相手の心理的ハードルが下がる。
これは「一貫性の原理」という心理が働くためである。
次に有効なのが「ドア・イン・ザ・フェイス」という手法である。
これは、最初に少し無理なお願いをし、それを断らせたあとで、本当に望む条件を提示するという方法である。
人は相手が譲歩してくれたと感じると、自分も譲歩しなければならないと感じる「返報性の法則」によって、次のお願いを受け入れやすくなる。
逆に「フット・イン・ザ・ドア」は、小さなお願いを受け入れてもらったあとに、徐々に本来の目的に近づける方法である。
たとえば、最初に「ちょっと意見を聞かせてほしい」とお願いし、その後で「具体的な対応を一緒に考えてほしい」と持ちかける。
小さな協力をすると、人は自分を「協力的な人間だ」と捉えるようになるため、大きなお願いにも応じやすくなる。
もう一つの重要なポイントは「沈黙の力」である。
交渉の中で、提案や質問をしたあと、あえて数秒間黙ることで、相手がプレッシャーを感じて先に譲歩するケースがある。
沈黙を怖がらず、堂々と待つ姿勢を見せることで、こちらの発言に重みが出る。
交渉の場面では、最初に自分から条件や金額を提示することも有効である。
これは「アンカリング効果」と呼ばれ、最初に出された情報が基準になってしまうという心理を利用している。
最初に少し強めの条件を出しておくと、そのあとに相手が提示する条件がその基準に引き寄せられる可能性が高くなる。
交渉が行き詰まったときは、相手に「あなたが私の立場だったらどうしますか」と聞いてみるとよい。
これにより、相手は一度冷静に立場を切り替えて考える必要が生じ、視点が広がる。
また、自分の立場を理解してもらいやすくなるため、話が前に進みやすくなる。
「NO」と言わせたくないときは、「やるかやらないか」ではなく「AとBどちらがいいか」と聞くとよい。
これを「二者択一法」といい、どちらの選択肢を選ばれても自分にとってメリットがあるように設定しておけば、交渉を自分のペースで進められる。
さらに、相手と自分を「対立する存在」と見せるのではなく、共通の敵や問題を設定することで「同じ側の人間」に見せることができる。
たとえば、「この条件、上の決裁が厳しくて…一緒にどう進めるか考えてもらえると助かります」といったように、外部の課題に一緒に取り組む姿勢を示すと、相手との距離が縮まりやすい。
これらのテクニックは、相手を操るためのものではなく、「お互いにとって納得のいく着地点を見つけるための手段」として使うことが大切である。
交渉が苦手だと感じる人ほど、こうした知識を味方につけることで、自然に話ができるようになるだろう。



コメント