人はつい他人を批判してしまうことがある。
ときには正義感から、ときにはイライラをぶつけたくなって、あるいは自分を守るために。
だが、その批判は自分の心を静かに傷つけ、ストレスの原因となることも多い。
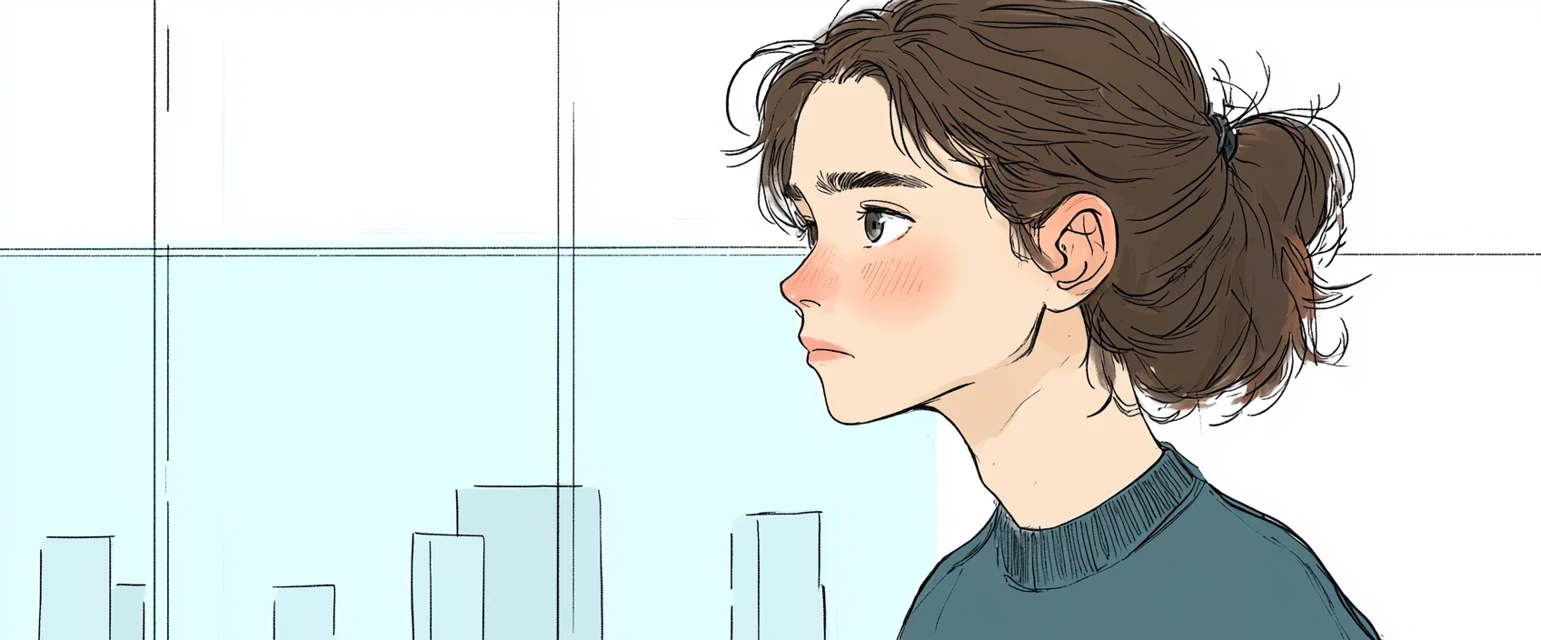
人間の脳には、他人と自分を完全に分けて処理するのが難しいという特性がある。
たとえば「あの人は本当にだらしない」と思った瞬間、脳の一部はその言葉をあたかも自分に向けられたもののように受け取ってしまう。
これを繰り返すと、他人への批判が自分への否定につながり、知らないうちに自己肯定感が下がるという悪循環が生まれる。

他人への怒りや不満が強いとき、それは実のところ自分自身に対する不安や不満の裏返しであることが多い。
脳にはミラーニューロンと呼ばれる仕組みがあり、他人の言動に自分のことのように反応する。
つまり、どうしても許せないと感じる他人の行動は、自分の中にも同じ傾向があるからこそ反応してしまっている可能性がある。
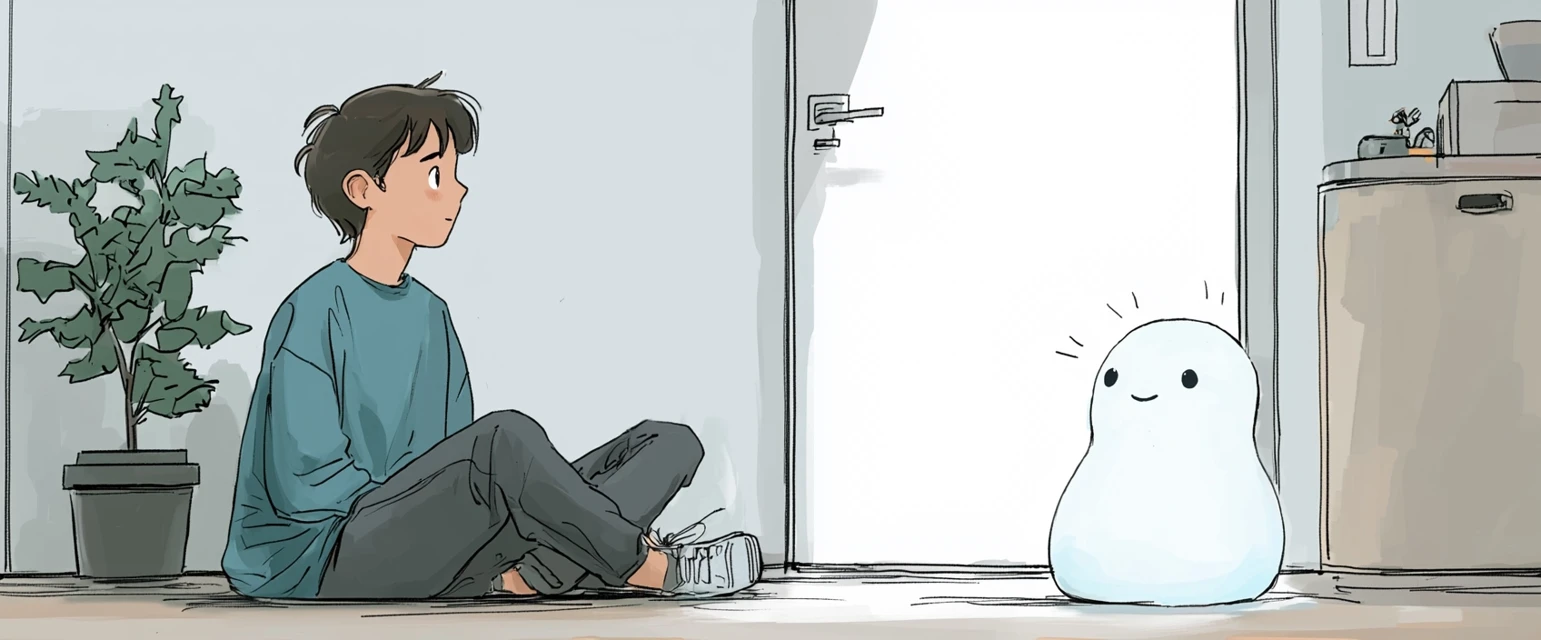
こうした傾向に気づいたときに役立つのが、自分の感情を客観的に観察する練習である。
たとえば、日常の中でイラッとした場面を一行日記のように書き出してみる。
そのうえで、そのときの相手に対して自分がどんな言葉を使っていたか、どんな印象を抱いたかを記録する。
そして最後に、「自分にも同じところはないだろうか」と問いかけてみる。
これは、他人への批判をきっかけに自分の内面を知るための手法である。
もう一つ有効なのは、心の中に「冷静な解説者」を登場させる方法だ。
感情が高ぶったとき、その状況をあたかもドキュメンタリー番組のナレーションのように語る。
たとえば、「人物Aは今日も会議に遅刻した。
背景には睡眠習慣の乱れがあるのかもしれない」といった具合に、感情的にならず事実を淡々と描写する。
これにより、自動的な批判の思考から一歩距離を置くことができる。
さらに、意識的に相手の立場に立って想像してみる練習も効果的である。
相手がなぜそのような行動を取ったのか、できるかぎり肯定的な理由を考えてみる。
これは事実かどうかは重要ではなく、「その人にも理由があるかもしれない」と思考の幅を広げることが目的である。
これを繰り返すことで、批判の癖が共感へと少しずつ変わっていく。
こうした練習を積み重ねると、他人を批判する前に一呼吸おく習慣が身につくようになる。
批判の癖は性格ではなく、ただの思考習慣である。
習慣は意識的に変えることができる。
つまり、自分の感じ方や考え方を少しずつ調整することで、他人との関係も、自分自身との関係も穏やかなものへと変わっていく。


コメント