共感疲労とは、他人の苦しみや悲しみに繰り返し触れることによって、自分自身の心がすり減っていく状態のことである。
人の感情に寄り添うことは、人間関係において重要であり、思いやりのある行動として評価される。
しかし、必要以上に感情移入しすぎると、自分の心にも深い負担がかかる。
この現象は、特に看護師や介護士、教師、カウンセラーといった、他人を支える職業に多く見られるが、一般の人でも起こり得る。
たとえば、SNSで他人の悩みや不幸を頻繁に目にしたり、友人の相談を長時間聞いたりする中で、自分自身が疲れてしまうという経験は、多くの人にとって身近なものだろう。
人が他人の感情に反応するのは自然なことである。
これは脳の仕組みによるもので、たとえば誰かが悲しんでいるのを見たとき、自分の脳も同じように反応する神経回路が存在する。
これにより、他人の気持ちを理解することができる。
しかし、こうした働きが過剰になると、他人の苦しみがまるで自分のことのように感じられ、心のエネルギーが消耗してしまう。
これが共感疲労の根本にある問題である。
人の苦しみに寄り添うこと自体は悪いことではない。
むしろ、共感できる能力は人間にとって大切な力である。
ただし、相手の感情にあまりにも強く巻き込まれてしまうと、今度は自分自身が無力感や虚しさ、怒り、疲労感などに襲われてしまう。
結果として、感情が麻痺したり、人との関わりを避けたくなったりすることもある。
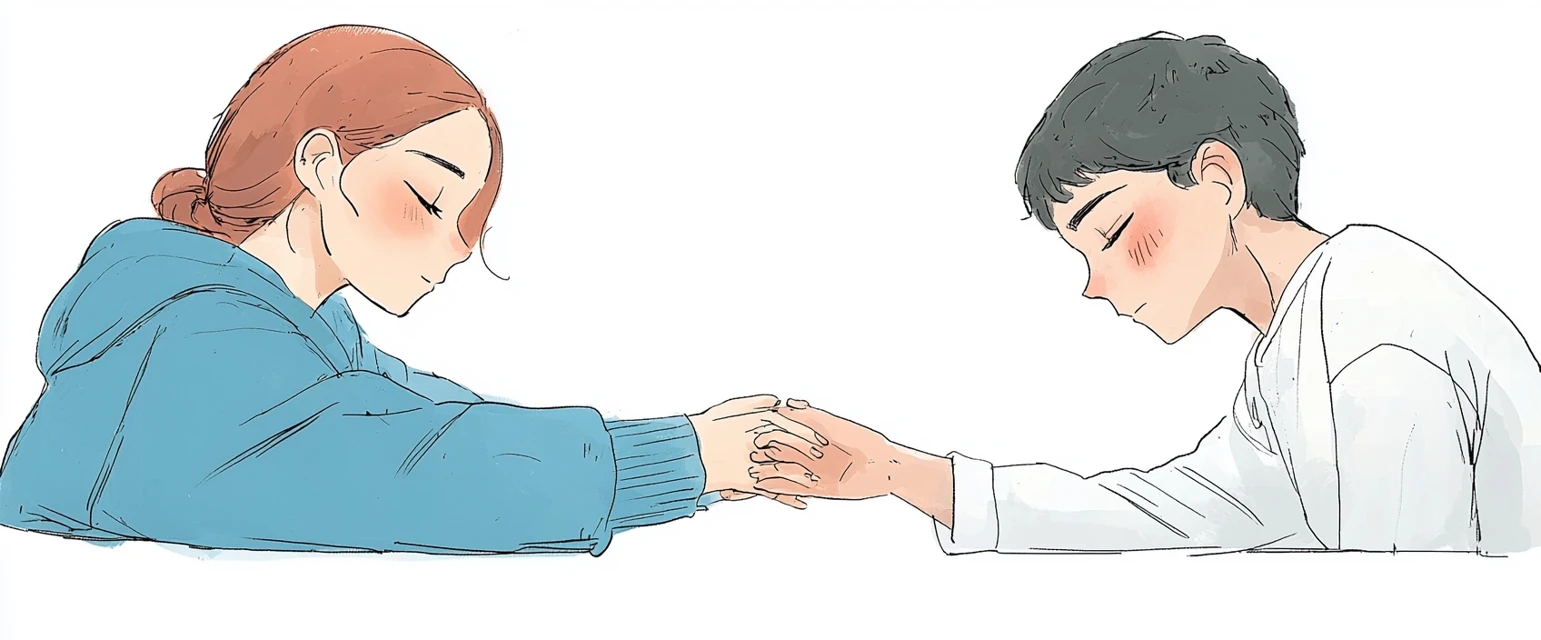
共感疲労に陥らないためには、いくつかの対処法がある。
まず、自分が感じている疲れが「共感によるもの」であると自覚することが出発点となる。
そして、自分がどのくらい相手に感情移入しているかを意識し、必要に応じて少し距離を取ることも大切だ。
これは冷たい対応ではなく、自分の心を守るための健全な方法である。
また、感情をため込まず、信頼できる相手と気持ちを共有することや、自分を癒す時間を持つことも有効である。
趣味や運動、自然とのふれあいなど、心をリセットできる習慣を日常に取り入れることが望ましい。
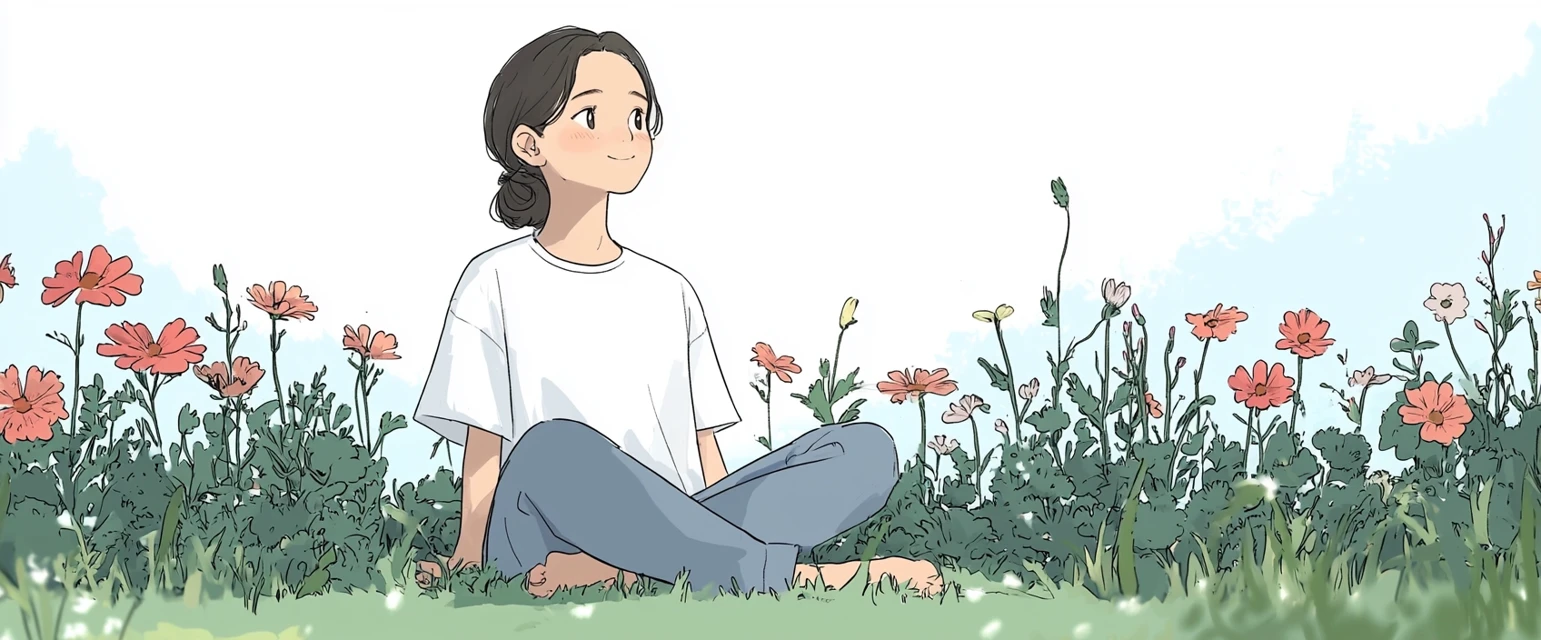
さらに、共感にはいくつかの種類があることを知ると、より良いバランスがとれるようになる。
相手の気持ちを理解する「認知的な共感」、相手の感情に同じように反応する「感情的な共感」、そして相手を思いやるが自分は冷静でいられる「思いやり(コンパッション)」がそれである。
共感疲労が起きやすいのは、感情的な共感が過剰になったときである。
思いやりの形で共感を持つことができれば、相手に寄り添いつつ、自分の心も保つことができる。
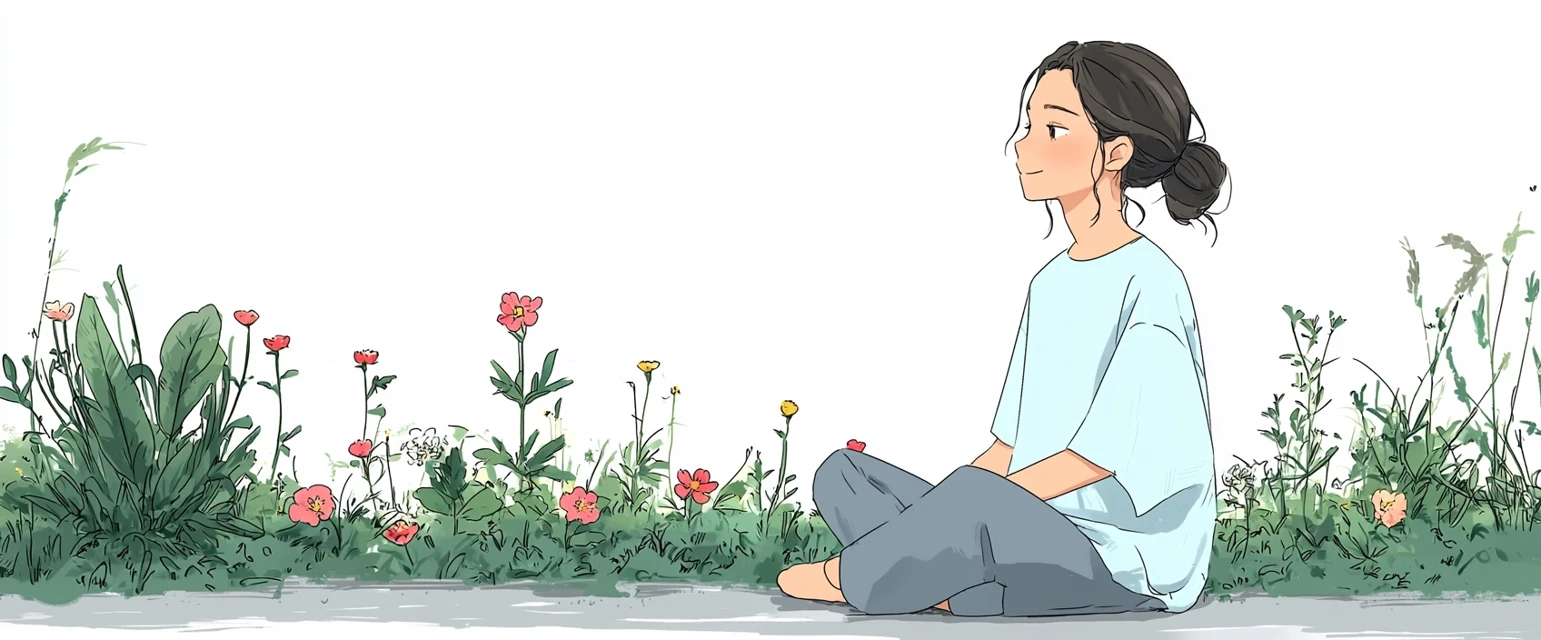
現代社会では、共感疲労のリスクは高まっている。
インターネットやSNSによって、遠くの他人の悲しみや怒りにも触れる機会が増えた。
それに加えて、共感しないことは冷たいとされる空気もあり、無理にでも感情移入しなければならないような圧力も感じられる。
だが、全ての感情に応じていたら、人の心はもたない。
共感は美しい力ではあるが、使い方を誤れば、自分を苦しめる原因にもなる。
大切なのは、自分の限界を知り、その範囲の中で他人と関わっていくことだ。

優しさは枯渇することがある。
そのことを知り、共感を上手に使いこなすことが、長く人に優しくあり続けるためのコツである。



コメント