人はなぜ言い訳をしてしまうのか。
この問いは、日常生活の中で一度は考えたことがあるだろう。
言い訳とはただの言葉の逃げ道ではなく、背後には深い心理的な背景や社会的な影響が潜んでいる。
私たちは皆、時には言い訳をしてしまうが、その理由を理解することで、自己成長の手がかりを見つけることができるかもしれない。

言い訳の背景には、まず過去の経験が大きく関わっている。
幼少期に厳しく叱られた経験や、失敗が大きな罰につながったことはないだろうか。
こうした経験は、失敗を恐れる気持ちを生み出し、自己防衛のために言い訳をする行動を誘発する。
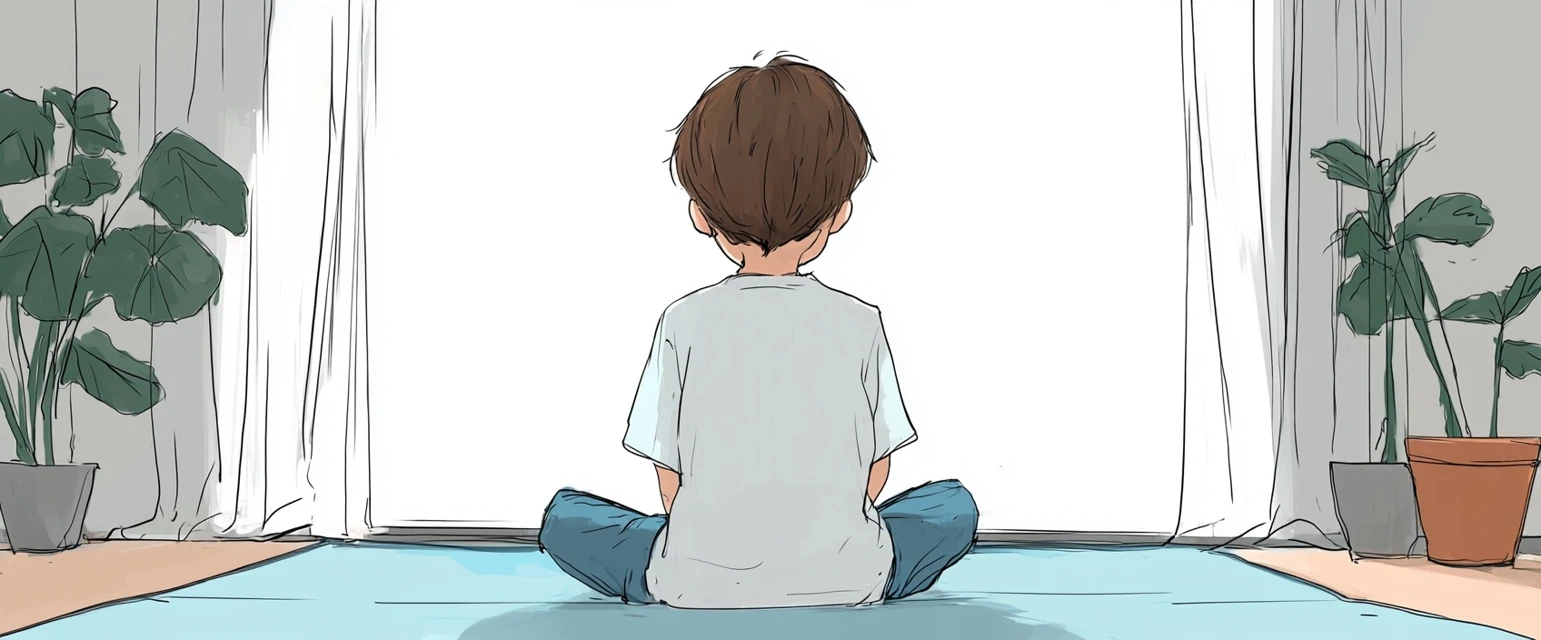
次に、自分をどう見るかという自己認識も重要である。
自分の価値や能力についての認識が不安定であると、他人からの評価に過度に依存するようになる。
このような場合、言い訳を使って自分の価値を守ろうとするのだ。
自己評価が低いと、他者との比較から劣等感を抱き、言い訳をしてその感情を和らげようとすることがある。
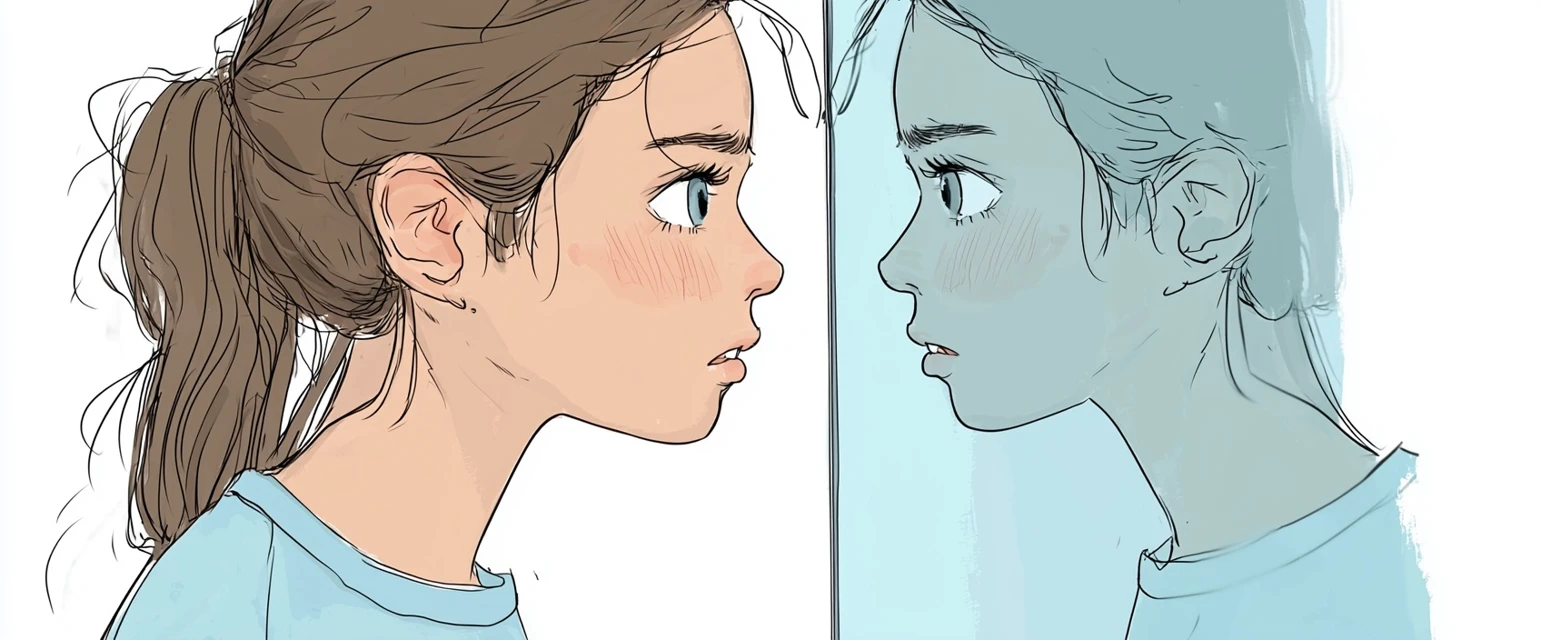
また、認知バイアスも言い訳を助長する要因となる。
自己奉仕バイアスが強いと、自分の成功を自分のものとし、失敗を外部要因に求める傾向が生まれる。
これにより、失敗を認めることが難しくなり、言い訳を使って事実を歪めることがある。
このような認知バイアスは、自己理解を妨げる要因となる。
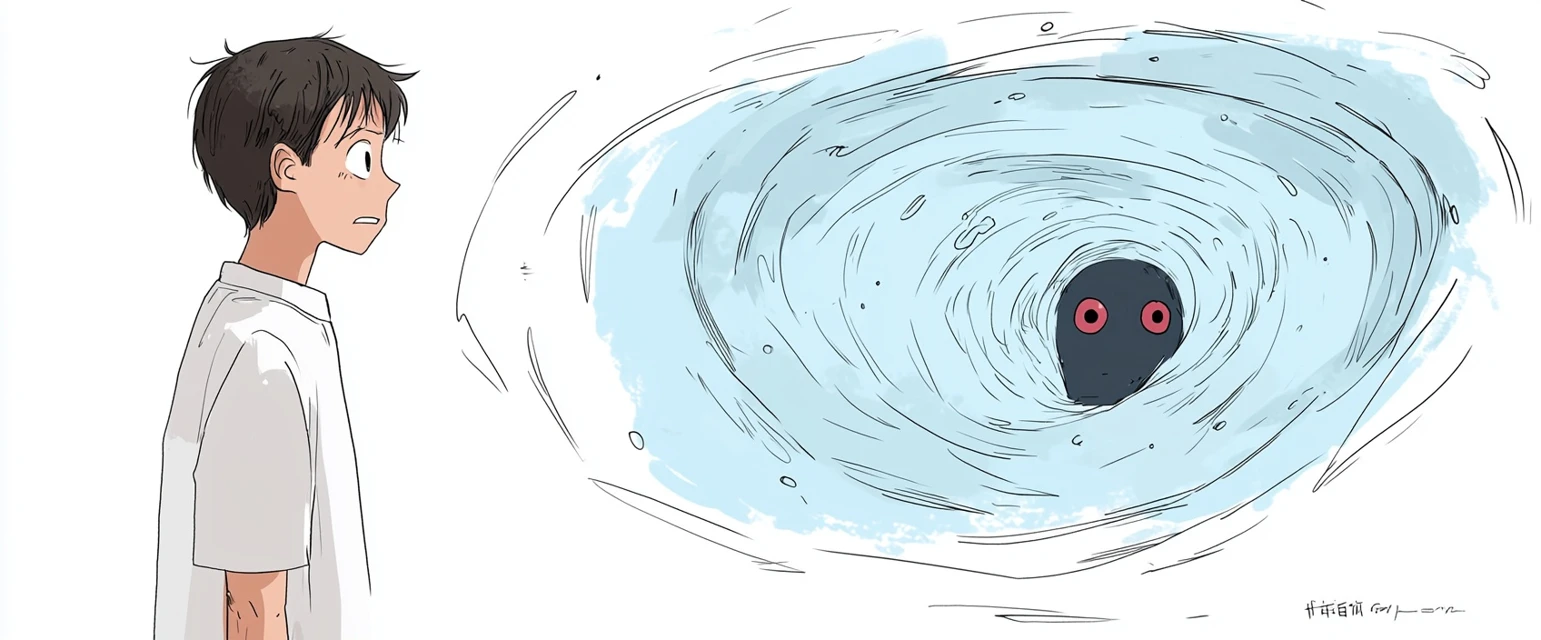
文化的背景も見逃せない。
文化によっては、失敗を厳しく非難する風潮がある。
こうした文化では、失敗を隠すために言い訳を多用することが増える。
逆に、失敗を学びの機会と捉える文化では、言い訳の必要性が低くなる。
文化的な態度が、言い訳の頻度に影響を与えているのだ。
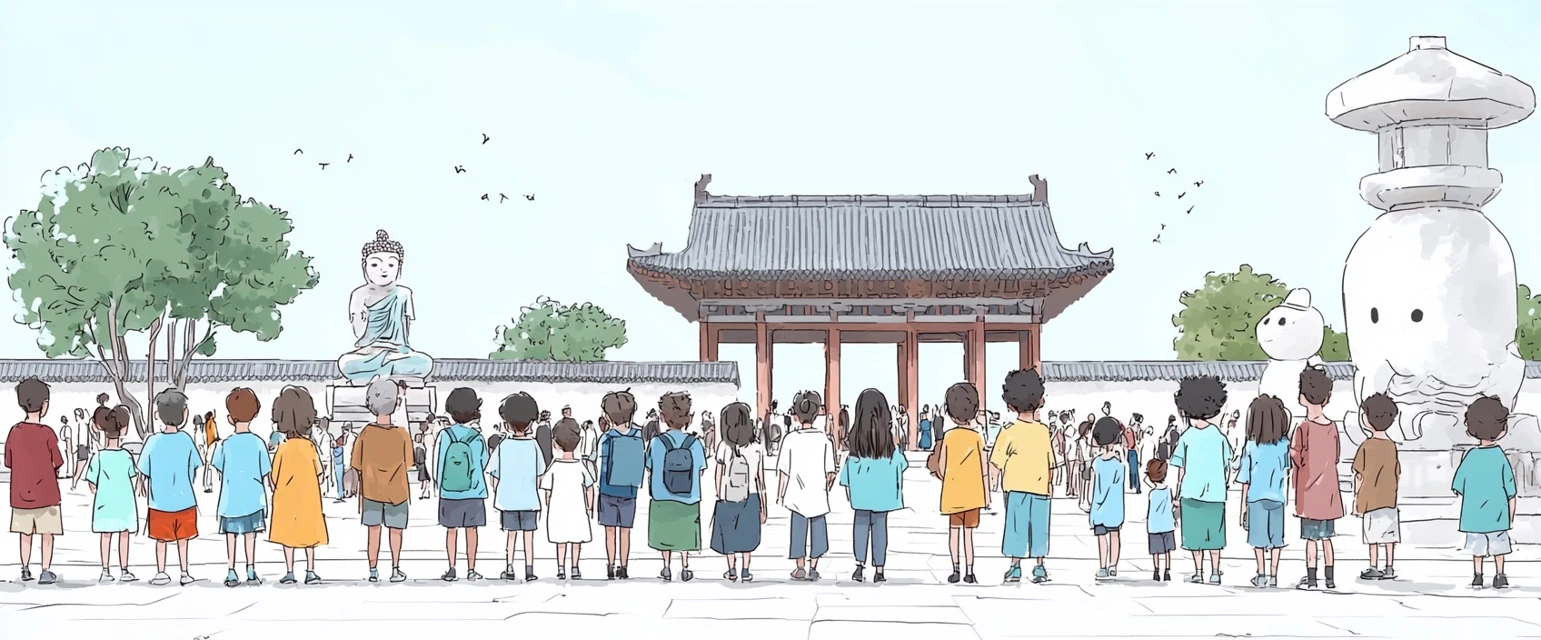
さらに、コミュニケーションスキルの不足も関係がある。
効果的に自分の意見を伝えたり、他者との対立を解決したりする能力が欠けていると、誤解を避けるために言い訳をすることが増える。
特に感情をうまく表現できない場合、言い訳が対話の手段となってしまうことがある。
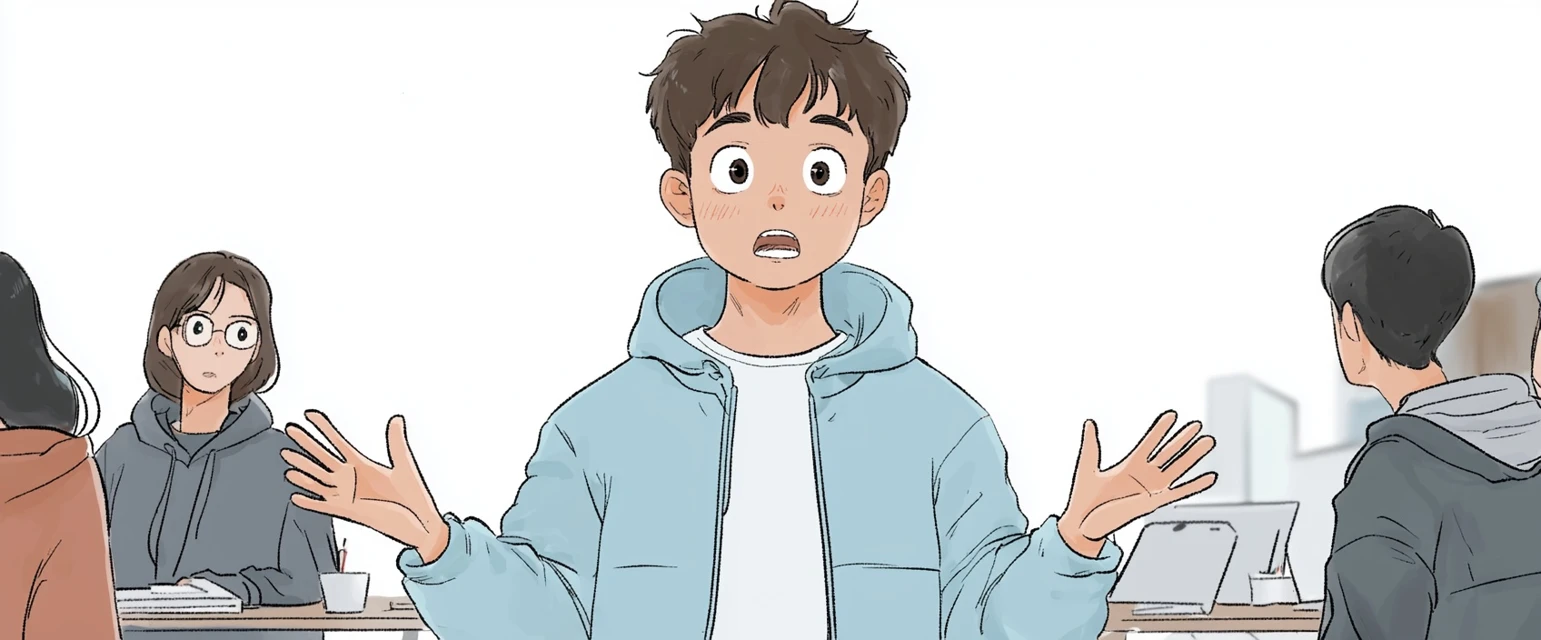
パーソナリティ特性も影響を与える要因である。
神経症傾向が高い人は不安やストレスを感じやすく、自己防衛のために言い訳をしがちだ。
これに対し、オープンで柔軟な性格の人は、失敗を自己改善の機会と捉え、言い訳をする必要性が低くなる。

最後に、モチベーションの問題も考慮すべきである。
内発的動機づけが低いと、外部の圧力や期待に応じて行動することが多くなり、結果として言い訳をして責任を回避しようとする傾向がある。
逆に、内発的動機づけが高いと、失敗を自らの成長の糧と捉えやすくなる。
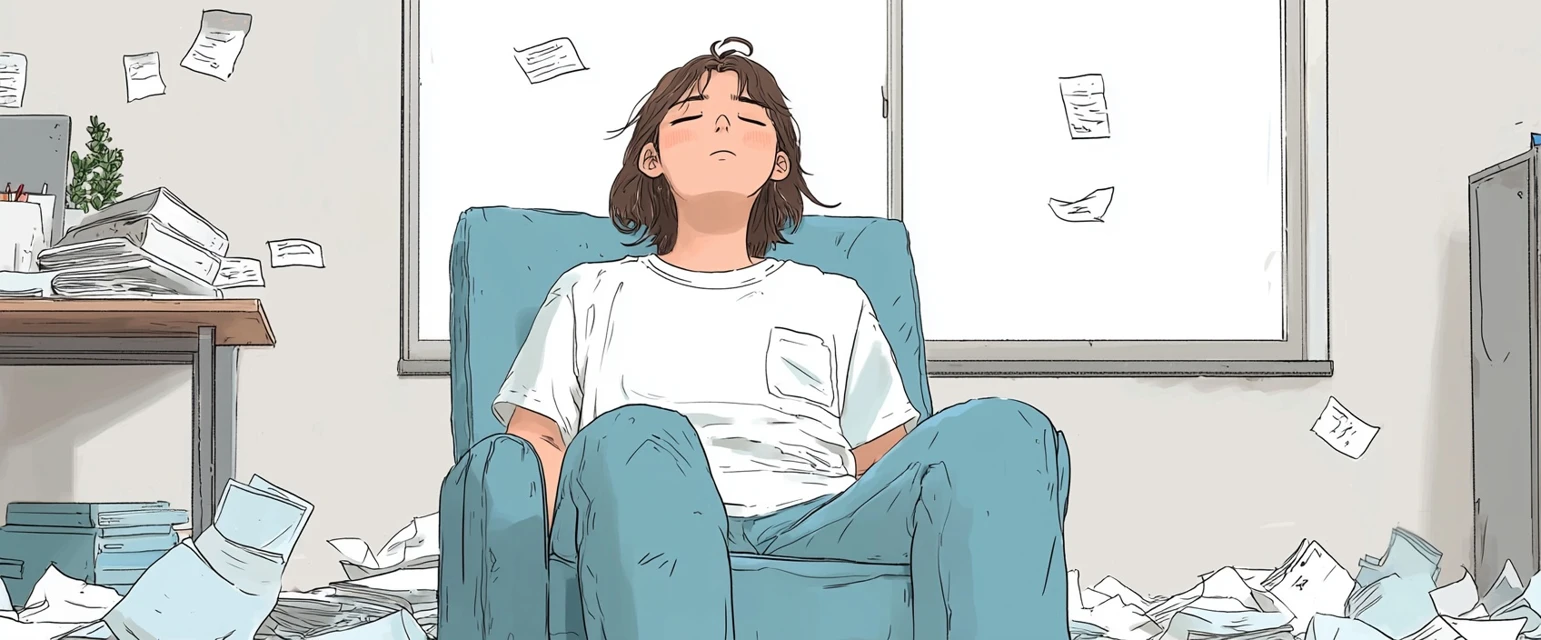
言い訳を減らすためには、これらの要因を理解し、自己認識を深めることが必要だ。
また、安心して失敗を受け入れ、学びに変えられる環境を整えることも重要である。
コミュニケーションスキルを向上させる努力も、言い訳を減らすための一助となるだろう。
これらの取り組みを通じて、言い訳をする代わりに自己成長を促す文化を育むことができるはずだ。
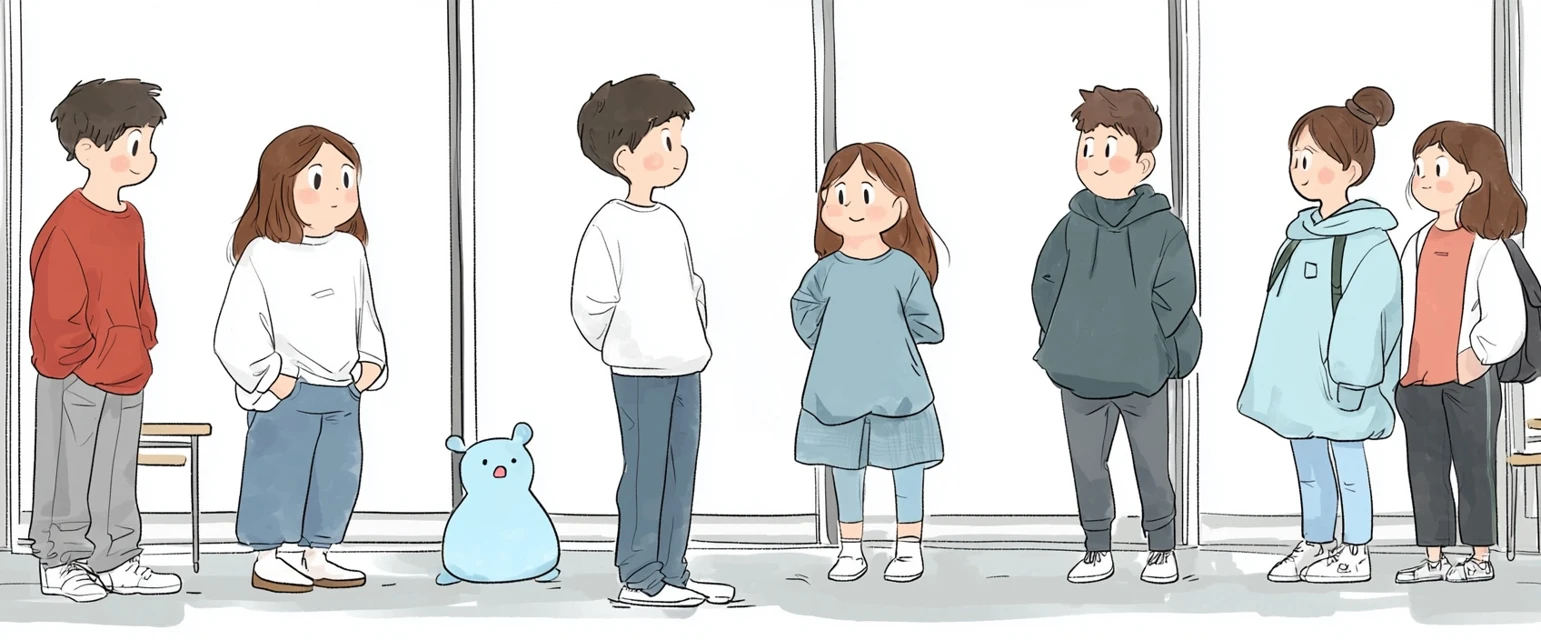

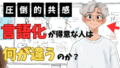

コメント